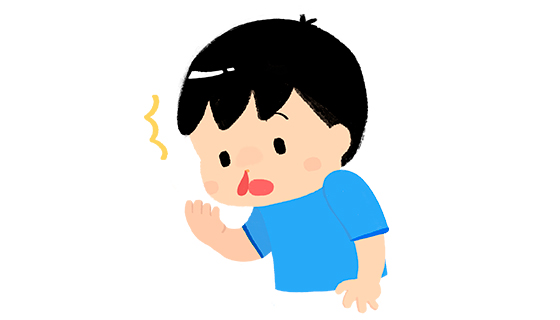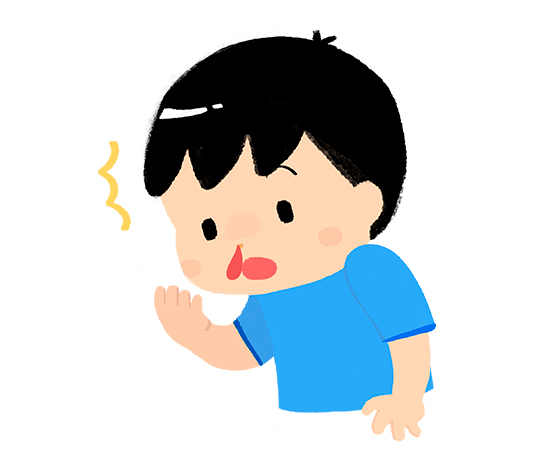mama知っ得!情報
梅雨時キッチンの食品管理術
気温も湿度も上がる梅雨時は、食材が腐敗・劣化しやすくなるもの。
いざ使おうと思ったらカビが生えていたり、湿気で傷んでいたり…。
みなさんもそんな経験があるのでは?
6~8月は、1年の中で特に食中毒が起こりやすいシーズンでもあります。
そこで今回は、梅雨時期の食品保存のポイントを、料理研究家の野口英世さんに教えていただきました。

カビさせない、腐らせない! 食品保存のポイント 〜生鮮食品編〜
細菌(黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌など)が引き起こす食中毒は、6~8月にかけて多く起こります。これは、気温が20℃を超えるあたりから細菌の活動が活発化するため。また、高温多湿な時期に増えやすいカビも、食中毒の原因となりえます。 「細菌は目に見えませんし、細菌による食材の変化は、見た目やにおいだけでは判断できません。カビの場合は、見た目やにおいでわかることもありますが、一見すると変化がなさそうな部分にも、菌糸が広がっていることがあります。だからこそ、日頃から細菌やカビを増やさないように意識することが大切です」(野口さん)
① 買い物は売り場を回る順番を考える
買い物時の“ちょっとした気配り”で、肉・魚が傷むスピードを遅らせることができます。食品を買うときは、常温のもの→野菜→肉・魚→冷凍食品の順に売り場を回って、肉・魚が常温にさらされる時間をできるだけ短くしましょう。
② 買い物後は保冷剤や保冷バッグを利用する
買い物が終わった後も油断は禁物。肉・魚には保冷剤を添える、あるいは保冷バッグに入れるのがベター。
買い物後に寄り道をして、食材を長時間持ち歩くのも避けましょう。
③ 傷む原因を取り除いてから冷蔵庫に入れる
自宅に戻ったら、食材をすぐに冷蔵庫へ!
なお、肉・魚のドリップ(食材に含まれる水分)には細菌がいることも。
ドリップが出ていたら、キッチンペーパーなどで拭き取ってから、清潔な容器に移し替えましょう。
野菜や果物に傷んでいる部分があった場合は、そこから細菌やカビが広がることもあるので、取り除いてから保存しましょう。
④ 早めに食べ切る
「冷蔵庫に入れたら、もう大丈夫!」と思いきや、そうとは限りません。
冷蔵庫は頻繁に開け閉めする分、中の温度や湿度が変化しがち。
温度や湿度の変化は鮮度劣化を早める原因にもなるので、扉を開けっぱなしにしないように注意しましょう。
また、冷蔵庫に入れても菌はゆっくりと増殖します(冷蔵庫に入れたからといって、菌が死滅するわけではありません)。
清潔な状態で保存することを心掛け、できるだけ早く食べ切るようにしましょう。
カビさせない、腐らせない! 食品保存のポイント 〜乾物(乾燥食品)編〜
乾物では食中毒は起こらないと思っていませんか? 過去には、刻みのりによる食中毒が起きています。
「乾物は湿気を嫌います。梅雨になる前に在庫を確認して、食べられるものは早めに食べ切ってしまいましょう」 と野口さん。
保管する際には、次のことに注意して!
① 水場の近くには保管しない
シンク下の収納庫など、水場の近くにのりや昆布を保管するのはNG。乾物は吸湿しやすいので、水場から離れた吊り戸棚やパントリーに保管しましょう。
② 見える化する
開封した乾物は、きちんと封をしたうえで、さらに中身が見えるチャック付きビニール袋に入れ、1カ所にまとめて保存するのが◎。
そうやって“見える化”しておくと、使うたびにすべての開封済みの乾物が目に入るため、「開封したまま忘れていた」「気づいたら賞味期限が過ぎていた」といううっかりミスも防げます。
③ 冷凍保存する
出汁昆布や干し椎茸などを長期保存したいときは、冷凍保存しましょう。出汁をとるときは、凍ったまま水に入れればOKです。
カビさせない、腐らせない! 食品保存のポイント 〜調理済み食品編〜
コロッケや天ぷら、焼きそばなど、スーパーやコンビニで購入したお惣菜を食卓に出しっぱなしにしたり、鍋に残ったカレーをコンロの上に置いたままにしたりはしていませんか?
「調理済みであっても、室温で放置するのは避けてください。また、においや見た目で『まだ食べられそう』と思っても、期限を過ぎたものや時間が経っているものは口にしないようにしましょう」(野口さん)
① 室温で放置しない
お惣菜を買う際もできるだけ保冷剤を使い、持ち帰った後は、再加熱して早めに食べるようにしましょう。
すぐに食べないときは、冷蔵庫で保存すること。カレーや味噌汁などをまとめて作って後日食べるような場合も、室温で放置せず必ず冷蔵庫で保存しましょう。
② 清潔な容器で保存する
保存の際に古くて傷の入っている容器を使うと、傷に雑菌が入っている可能性も…。
食べ切れなかったお惣菜や料理を保存するときは、清潔な容器を使うようにしましょう。
梅雨から夏にかけては、チャック付きビニール袋などの使い捨てできる保存袋を活用するのがおすすめです。
③ 食べるときはしっかり加熱する
レンジやガスコンロなどで温め直す際は、いつもより長めに、しっかりと加熱しましょう。
作り置きの煮物や食べきれなかった汁物を温めるときは、たとえ気温が高い日でも、沸騰するまで温めるのがポイントです。
食品だけでなく、キッチンアイテムにも気を配って!
食器用スポンジやまな板、包丁なども、細菌が付着・増殖しやすいといわれています。 キッチンまわりのアイテムを清潔に保ち、調理中に細菌が食材に付着しないように気をつけましょう。加えて、手洗いを徹底することもお忘れなく!
① まな板は使うたびに洗う
まな板は、野菜用、肉用、魚用といった具合に食材別に用意するのがベストです。難しい場合は、1つの食材を切り終えたら、そのつど、食器用中性洗剤できちんと洗いましょう。また、肉や魚を切った後、そのまま野菜を切るのも避けるべき。肉や魚に付着していた細菌が、野菜についてしまう可能性があるからです。野菜→肉・魚の順番で着ることを習慣づけるといいでしょう。
なお、1日の終わりには、食器用中性洗剤で洗ったまな板に熱湯をかけ、風通しのいいところに立てかけて乾かしておきます。包丁も、1つの食材を切り終えるたびにしっかりと洗ってください。
② 食器洗い用のスポンジにも要注意!
食器洗い用のスポンジも、菌の温床になりがちです。お皿を洗い終わったら、食材のかすが残らないようにスポンジもよく洗ってください。除菌ができる洗剤を使っている場合は、洗剤の表記に従ってスポンジを除菌し、清潔を保ってください。なお、スポンジは3週間から1カ月をメドに取りかえることをおすすめします。
「すべてを実践するのは難しい」という声も聞こえてきそうですが…。
「今回ご紹介したのは、普段の調理や買い物、保存場所などをほんの少し見直すだけの方法。
いったん習慣化できれば、さほど難しいことではないはずです!」と野口さん。
細菌の活動が活発になる梅雨の季節を安心・安全に乗り切るために、ぜひ実践してみてください!

野口英世/料理研究家、フードスタイリスト
ファッショナブルさとおいしさを兼ね備えたスタイルの料理や、無理なく作ることができるスマート時短レシピに定評がある。『turk フライパンクックブック』(誠文堂新光社)など著書多数。
※当記事は野口さんへの取材および下記資料をもとに構成しました。
【参考資料】
政府広報オンライン『食中毒を防ぐ3つの原則・6つのポイント』
厚生労働省『家庭でできる食中毒予防の6つのポイント』