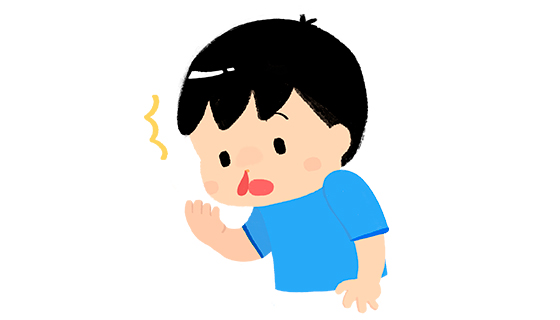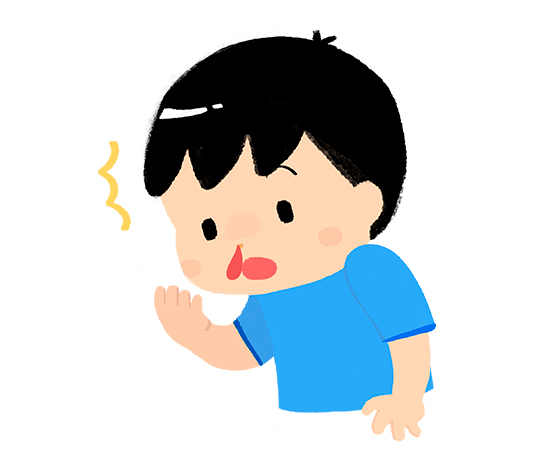mama知っ得!情報
産後ケアにも効果的! ベビーヨガで赤ちゃんとスキンシップを

自分のペースで無理なく取り組める運動として人気のヨガ。妊娠中にマタニティヨガを楽しんだ方も多いのではないでしょうか。ヨガインストラクターの築山萌さんは「年代を問わずにできるヨガは、実は赤ちゃんとママにもぴったり!」と話します。親子のスキンシップやママのリフレッシュに、おうちでできるベビーヨガを取り入れてみませんか?
ベビーヨガって何? いつから始められる?
ベビーヨガとは、ママやパパと赤ちゃんがペアで行うヨガのこと。目安として、首がすわる3〜4カ月頃から1歳6カ月頃まで楽しむことができます。
一般的なヨガはひとりでポーズを取るものなのに対し、ベビーヨガは親子で一緒に動くのが最大の特徴です。赤ちゃんの成長に合わせたポーズを取り入れることで、親子のスキンシップを深めるほか、赤ちゃんの発達のサポートにもつながり、産後のママにとっては体型戻しの効果も期待できます。
ベビーヨガの始めどきは、赤ちゃんの首がしっかりすわっていることが目安です。生後3〜4カ月頃からが目安ですが、赤ちゃんの発達には個人差があります。
●腹ばいにすると、自分で頭を持ち上げられる
●縦抱きにしたときに、頭がグラグラせずに保てる
以上の首すわりのサインを確認してから始めましょう。
ベビーヨガを行う際には、ママやパパは締め付けの少ない動きやすい服装を選びます。赤ちゃんは普段着慣れた洋服でOK!部屋が暖かければ、肌着でもかまいません。また、ヨガマットはあればベストですが、ない場合はバスタオルやブランケットなどでも代用可能です。
ベビーヨガにはどんな効果があるの?
ベビーヨガには、親子ともにさまざまなメリットがあります。
まず、赤ちゃんにとっては、肌の触れ合いから安心感を育み、親子の絆を深めることができるのが大きなポイント。愛着形成は、赤ちゃんの心の安定に欠かせません。
ベビーヨガを取り入れているママからは、「夜、ぐっすり寝てくれるようになった」「夜泣きが減った」という声もよく聞かれますよ。
また、発達の面からも、肌の触れ合いで得る刺激は重要です。
感覚神経への刺激は、脳や体の発達をサポートするといわれています。さらに、月齢や発達に合わせてベビーヨガのポーズを行うことで、バランス感覚や運動機能の発達も促されます。
一方で、大人にとっても、赤ちゃんとの触れ合いは癒し効果抜群! 赤ちゃんと触れ合うと、「愛情ホルモン」とも呼ばれるオキシトシンの分泌が促進されるため、心が落ち着き、穏やかで満ち足りた気持ちに導かれるのです。
特に、産後のママはホルモンバランスが乱れがち。慣れない育児で「思うようにできない」「赤ちゃんの気持ちがわからない」など、自分を責めてしまうこともあるかもしれません。ベビーヨガには、新米ママ&パパの張り詰めた緊張をほぐし、赤ちゃんの気持ちよさそうな表情に、親としての自信を積み重ねていく機会にもなります。
また、ヨガのゆったりした動きは、ホルモン分泌や自律神経のバランスを整えるのにも役立つほか、骨盤を正しい位置へと調整する効果も。産後のリカバリーとシェイプアップにもおすすめです。
ベビーヨガを行う際の注意点4つ
安全にベビーヨガを楽しむためには、いくつか覚えておきたいポイントがあります。
① 授乳や離乳食からは20分以上間隔をあける
赤ちゃんの胃はとっくり状で、食べ物を吐き戻しやすい構造になっています。授乳や離乳食後はゆったり過ごし、消化に負担をかけないことが大切です。ベビーヨガは、授乳・離乳食のあとは避け、赤ちゃんの機嫌のいい時間を選んで行いましょう。
② 5〜10分の短時間から始める
初めてベビーヨガに取り組むときは、5〜10分の短時間から始め、慣れてきたら少しずつ時間を延ばしていくといいでしょう。赤ちゃんがぐずったり、眠そうな様子が見えたら、無理せず中断し、休みましょう。
③ ソフトタッチが基本!
赤ちゃんの筋肉や関節は大人に比べてやわらかく、繊細です。強い力で曲げ伸ばしをしたり、正しいポーズをしようと無理に動かすことのないように注意しましょう。やさしく、心地いい触れ合いを楽しむことが大切です。
④ ベビーヨガ後は授乳か水分補給を
ベビーヨガが終わったら、水分補給も忘れずに。授乳中の赤ちゃんならば、母乳やミルクを飲みたがるだけ与えます。離乳食が始まっているならば、白湯や麦茶などで軽くのどをうるおす程度でもいいでしょう。ママ・パパ自身も、体を動かしたあとはしっかり水分をとって、循環を促しましょう。ヨガの最中にも、いつでも水分補給ができるように、近くに水分を準備しておくのもおすすめです。
おうちで簡単にできるおすすめポーズ3選
赤ちゃんの発達別に、おすすめのポーズを選びました。初めてヨガをするママ&パパも、気軽にトライできる簡単なポーズです。赤ちゃんの表情を見ながら、親子でゆっくり楽しみましょう。
◎ねんねベビーにおすすめ!「赤ちゃんのポーズ」

写真提供:一般社団法人日本ハッピーライフ協会
首がすわった3〜4カ月頃からの赤ちゃんにおすすめのベビーヨガです。
まず、赤ちゃんを仰向けに寝かせ、ママは赤ちゃんと向かい合う位置に、あぐらをかいて座ります。赤ちゃんの足首を包むよう持ったら、ぶらぶらとやさしく揺らしてリラックス。ママはゆっくり息を吸い、ふーっと吐きながら赤ちゃんの足をおなかに近づけるように曲げましょう。「1、2、1、2」とリズムをとりながら、片足ずつ交互に曲げ伸ばしをするのもよいでしょう。
◎おすわりベビーにおすすめ!「飛行機のポーズ」

写真提供:一般社団法人日本ハッピーライフ協会
空を飛ぶような感覚を楽しみながら、バランス感覚や背筋を鍛えられるポーズです。
ママ(パパ)は、マットの前方に座って足をそろえ、すねに赤ちゃんをうつぶせに乗せます。赤ちゃんの背中を支えながら、ゆっくり後ろに倒れ、すねを床と並行に。「飛行機だよ、ぶーん」と声をかけながら、やさしく左右にひざを傾けましょう。赤ちゃんが楽しんでいる様子を見ながら、動きを止めたときには、腹筋を使って体を起こし、「いないいないばあー!」と赤ちゃんと顔を近づけるのも楽しいですね。このポーズは、赤ちゃんの感覚を刺激するだけでなく、ママの骨盤調整や腰痛の緩和にも効果的です。
◎はいはい&あんよベビーにおすすめ!「ベビードッグ」

写真提供:一般社団法人日本ハッピーライフ協会
親子でヨガの基本的なポーズ「ダウンドッグ」にチャレンジ! 「自分で動きたい!」という意欲が高まるはいはい・あんよ期の赤ちゃんにぴったりです。
赤ちゃんに四つんばいのポーズをとらせ、後ろからやさしくおしりを持ち上げるように手を添えます。このときママ(パパ)が顔を床に近づけて、のぞきこむようにすると、赤ちゃんも両手の間から目線を合わせてくれるかもしれません。手で床をしっかり支えることで、腕力や足腰のトレーニングにもなる動きです。
赤ちゃんが慣れてきたら、ママ(パパ)も向かい合って、同じようにダウンドッグでゆったりした呼吸を味わいましょう。
大人も、四つんばいになって手は肩幅に開き、肩の真下に置きます。膝は腰幅に開いて、腰の真下にセットしましょう。息を吐きながら腰を天井方向に持ち上げ、体を逆Vの字にします。膝は無理のない範囲で伸ばし、ゆっくり深い呼吸で20〜30秒ほどキープし、四つんばいに戻ります。
ママ自身の心身にも目を向ける時間に
ママにも赤ちゃんにもうれしい効果がいっぱいのベビーヨガ。親子のスキンシップやリフレッシュのひとつとして、取り入れてみてはいかがでしょうか。
初めての子育ては、わからないことばかりで不安も多いですね。私自身、新米ママの頃は泣いている我が子を見て途方に暮れてしまったこともありました。そんなとき赤ちゃんと一緒にヨガをしてみると、子どもの笑顔に元気をもらったり、体を動かすことで心身ともにリフレッシュできることに気づいたんです。ヨガには、「アヒムサ」といって、自分も他人も傷つけず、大切にするという考え方があります。この考え方は、産後のママに寄り添い、マッチするものだと感じています。
最近では、ベビーヨガのクラスを開講しているヨガ教室も増えています。おうちで楽しむほか、近くのベビーヨガ教室に参加するのもよいでしょう。さまざまなポーズを楽しめるほか、子育てのコミュニティづくりにも役立つかもしれません。
ヨガの醍醐味は、“気づき”です。ベビーヨガを通じて、赤ちゃんや自分自身の心と体に意識を向けていくと、たくさんの発見があると思います。赤ちゃんが産まれると、親はつい自分を後回しにしがちですが、ベビーヨガの時間は赤ちゃんだけでなく、自分自身の心と体にも目を向け、いたわってあげてくださいね。

築山 萌/一般社団法人日本ハッピーライフ協会【JAHA】代表講師
24歳の頃からヨガやピラティスのフリーインストラクターとして活動。2014年、一般社団法人日本ハッピーライフ協会を設立。自身の経験から妊活ヨガ、マタニティヨガ、産後ヨガ、ベビー&キッズヨガと、ヨガを通して産前・産後のママをトータルでサポートする活動に力を注ぐ。
https://jahayoga.com/