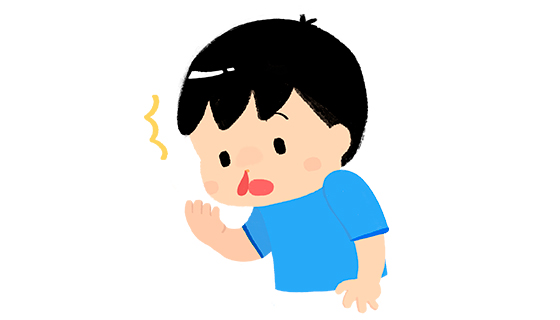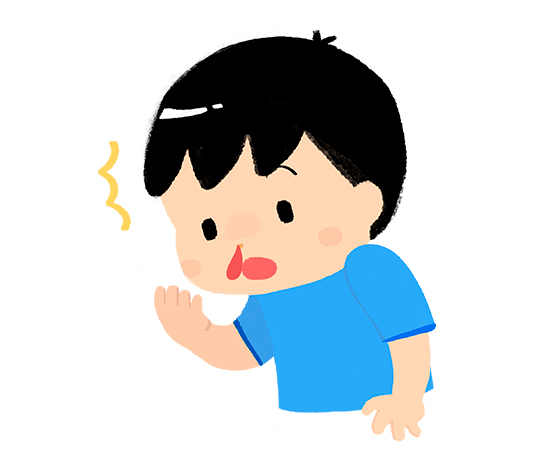mama知っ得!情報
この夏要注意! 小児科医が教える熱中症対策

記録的な猛暑となっている今夏の日本列島。9月上旬まで暑さが続くといわれる中、気をつけなければならないのが熱中症です。特に、自分の体調の変化をうまく伝えられない小さなお子さんには注意が必要! 今回は、子どもたちを熱中症から守る方法について、『小児科医ママの子どもの病気とホームケアBOOK』を出版したばかりの小児科専門医・森戸やすみ先生に聞いてみました。
「熱中症」について、しっかり理解できていますか?
気温が30度を越える真夏日が続く今年の夏は、テレビや新聞で「熱中症に注意」というフレーズを目にしない日がないほど。ところでみなさんは、熱中症がなぜ起こるのか、どういった症状がみられるのかなどについて、しっかり理解できていますか?
熱中症とは、暑さのせいで体温調節機能がうまく機能せず、からだに様々な異常が起こること。代表的な症状としては以下のものが挙げられます。
●熱失神 ………… めまい、立ちくらみ、意識を失う
●熱疲労 ………… 体のだるさ、気持ち悪さ、頭痛
●熱けいれん …… 筋肉のけいれん
●熱射病 ………… 体温の上昇、ぼーっとする、うわごとを言う、意識を失う
「子どもは、体温調節機能が大人に比べて未発達。からだが小さく温まりやすいのに、熱を逃がすことが上手ではないので、どうしても熱がこもりやすくなります。加えて、からだが小さい分、熱中症予防に必要な水分や塩分のストックも少なめ。だからこそ、子どもにとって夏の暑さはハイリスクなのです」(森戸先生)
とはいえ、子どもは、夢中で遊んでいてからだの異変に気付かなかったり、体調の変化をうまく表現できなかったりすることも。周囲の大人が「異変がないかどうか」をしっかりと見守るようにしてください。
気をつけるべき「熱中症の危険サイン」はこれ!
では次に、注意するべき「熱中症の危険サイン」を紹介します。子どもと遊びに出かける際は、次の10項目を気にかけるようにしましょう。
①歩行がふらついている、もしくは歩けるのに歩きたがらない
②顔が赤くなっている
③遊ばなくなる
④吐く
⑤いつもより汗が多すぎる、もしくは少なすぎる
⑥熱が高い
⑦肌が乾燥している
⑧自分で水分をとれない
⑨呼びかけに反応しない
⑩まっすぐ歩けない
「この中で、⑧〜⑩は特に危険な症状。⑧の場合は医療機関を受診し、⑨⑩の場合はすぐに救急車を呼ぶようにしてください」(森戸先生)
もしも熱中症になってしまったら…どうすればいい?
「熱中症かも」と思ったときは、あわてずに次の応急処置を施してください。⑧~⑩の場合も、救急車を呼ぶまでの処置として行いましょう。
1.休ませる
涼しい場所に移動し、衣服などのしめつけがない状態にして寝かせましょう。めまい、頭痛、気持ち悪さを訴えているときは、足を頭より高い位置に調節してください。
2.水分補給
用意できるのであれば経口補水液やスポーツ飲料を少量ずつこまめに飲ませましょう。水分補給の際は、100㎖に対して40~100㎎のナトリウムを含有しているもの(スポーツ飲料はこれに当てはまります)が理想的ですが、もし、手に入らなければ水でも構いません。とにかく水分をとるようにしてください。
3. からだを冷やす
体内の温度を急速に下げるには、氷を入れた水風呂に全身を浸からせることが効果的です。水風呂の用意が難しい場合は、からだを水で濡らしてうちわであおぐ、氷枕や保冷剤を首やわきの下、脚のつけ根にあてるなどの方法をとりましょう。
もし、処置をしても回復しない場合は、小児科を受診するか、救急車を呼ぶなどして対応してください。また、呼吸や心拍がない場合は心肺蘇生術(人工呼吸と心臓マッサージ)をしましょう。
熱中症にさせないために、覚えておきたい4つのこと
最後に、誰にでもできる熱中症の予防対策も紹介しておきます。子どもを熱中症のリスクから守るためにも、ぜひ覚えておいてください。
1.水分と塩分を補給する
こまめに水分と塩分を補給させましょう。塩分補給として、普段の食事に塩気のあるおやつをプラスしてみるのもおすすめです。
また、生後6か月までの赤ちゃんは母乳と粉ミルクで定期的に水分補給を。粉ミルクは薄めなくても大丈夫です。
2.涼しい場所でひと休み
外で遊ぶ際は、必ず日陰や涼しい場所での休憩を入れるようにしましょう。特に、顔が赤くなっていたり、大量の汗をかいていたりするときは、クーラーの効いた涼しい場所に移動を。ちなみに、『汗をかかないと汗腺が発達しない』と言う人もいますが、それは間違いです。暑い日にあえて屋外遊びに連れ出す必要はありません。
3.服装にも注意する
帽子をかぶらせることはもちろん、色の薄い服を着用させることもポイント(色が濃いものは熱を吸収しやすいため)。タンクトップやショートパンツではなく、袖や裾のあるものを選ぶとあせもの防止にもなります。
4.こどもを一人きりにしない
「少しの時間だから」「寝ているから」と子どもをクーラーのついていない屋内に一人きりにすることは絶対にやめてください。特に車内への置き去りは、毎年のように死亡事故に発展しています。冷房をつけたままであっても、数分の用件であっても、必ずお子さんと一緒に行動してください。
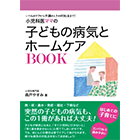
森戸やすみ/小児科医 一般小児科、NICU勤務を経て、現在は世田谷のさくらが丘小児科クリニックに勤務中。「小児科医ママの子どもの病気とホームケアBOOK」(内外出版社)が好評発売中。
さくらが丘小児科クリニック:http://sakuragaokashonika.com/
小児科医ママの子どもの病気とホームケアBOOK
※当記事は森戸先生への取材と上記著作の内容をもとに構成しました。