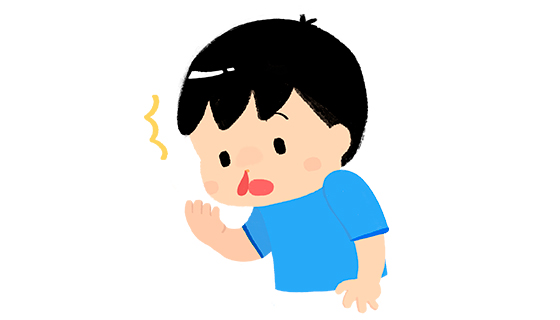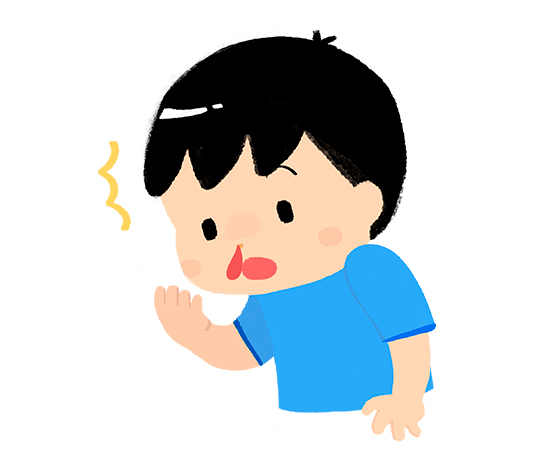mama知っ得!情報
住宅ローンの基礎知識

最初に「いくら借りるのか?」を設定することが大事
家を買うときに「何から考えるべきかわからない」という声をよく聞きます。「どの地域がいいか?」「どこの駅がいいか?」「戸建て?マンション?」「どんな間取り?」など、考えることはたくさんありますが、最初に決めておきたいのは「いくら借りるのか?」ということ。つまり、借入額(ローン)です。マイホームは人生の中でいちばんと言っていいぐらい大きな買い物。返済も長期間続くので、地域や間取りの前に、まずは家計に無理のない借入額がいくらなのかを考えるべきです。それでは、「借入可能額がどうやって決まるのか?」から説明していきましょう。
借入可能額は、「手取り」ではなく「年収」で決まる
住宅ローンは金融機関から借りるのが一般的。その際、貸し出す金額の基準となるのは、年収に対する「返済比率」です。返済比率というのは、1年間の返済額の年収における割合のこと。たとえば年収500万円の人が、年間150万円の住宅ローンを支払った場合、150万円÷500万円×100(%)ですので、返済比率は30%となります。そして、この返済比率の数値が大きくなると返済が滞るリスクが高まるため、融資が受けられなかったり、借入額を減らされたりするケースが出てくるわけです。
多くの金融機関は返済比率を公にしていませんが、唯一、住宅金融支援機構だけは返済比率を公開しています。住宅金融支援機構では民間金融機関と提携して、『フラット35』という住宅ローン商品を提供しており、これを活用すれば年収350万円を超える人は返済比率35%まで、年収350万円未満の人は返済比率30%まで借りることが可能です。
ここで注意したいのは、金融機関が返済比率を決める基準が「手取り」ではなく「年収」だという点です。ご存じの通り、年収とは税金や保険料が差し引かれる前の年間の総支給額のこと。一方の手取りは、年収から社会保険料、所得税、住民税などを引いた後に銀行に振り込まれる給与等の金額で、一般的に年収の7〜8割だと言われています。つまり、年収の30%という数字は、手取りの40〜50%に相当することもあるのです。
だからこそ、銀行が示す借入可能額はあくまで目安と考えて、「現実的に毎月どのくらいまでなら支払い可能か」を基準に返済額を設定するようにしましょう。「月々いくらまで抑えるべきか?」についての正解は残念ながらないのですが、参考までにお伝えしている基準は「手取りの3割」です。
毎月の生活から、現実的な「借入額」を考えましょう
では、さっそく現実的な「借入額」をシミュレーションしていきましょう。以下は、住宅ローンを金利1%で借りた時の返済額を表にしたものです。

35年返済のローンで、4,000万円を借りた場合と5,000万円を借りた場合の毎月の返済額を比較してみると、141,142円−112,914円=28,228円。さほど差のない金額に思えますが、ここでも注意すべきことがあります。それは、返済期間における金利の上昇です。

上記の表は、35年ローンの場合、金利の変動によって毎月の返済額がどのくらい変わるかを示したものです。金利が2%に上がった場合、5,000万円を借りた場合の毎月の返済額は165,631円。金利1%と比べると約24,500円も返済額が増えることになります。
借入額を手堅く設定するのであれば、金利が上昇した場合でも負担にならない程度に、毎月の返済額を抑えるといいでしょう。
長期間払い続けるからこそ、無理のない設定を!
数々の相談を受けてきて感じるのは、共働き家庭のほうが、借入額のシミュレーションを甘く設定してしまっていること。お互いの年収がマックスの状態(フルタイムで働き、残業代も含めた状態)で設定してしまうためです。子どもができると、育児休暇中の収入減、子育て期間中の短時間勤務による収入減に加えて、保育園や幼稚園の保育料負担、習い事などの教育費の負担がかさみます。転勤のため、どちらかが仕事を辞めざるを得ないケースもあるかもしれません。
また、仮に35年ローンだとしたら、その期間は想像以上に長く、返済期間中に生活や考え方ががらりと変わったりもするものです。だからこそ、銀行の「借入可能額」を鵜呑みにするのではなく、手取りの3割以内、共働きの場合はどちらか一方の年収を基準にして、「借入額」を設定することをおすすめします。

高橋成壽/ファイナンシャルプランナー 慶應義塾大学在学中に将来の独立を目指して、簿記の資格を取得。大学在学時よりヘッジファンド等投資・投機に関心を持ち、卒業後は商品取引会社に入社。営業、人事、総務などを経験し、ファイナンシャルプランナー(FP)の資格を取得した後、FPとしてのキャリアアップのために外資系生命保険会社に転職。2007年に寿FPコンサルティング株式会社を設立し、主に女性のためのマネープラン提供を手掛けて、独立後10年で1,000世帯を超える家庭にアドバイスを提供している。