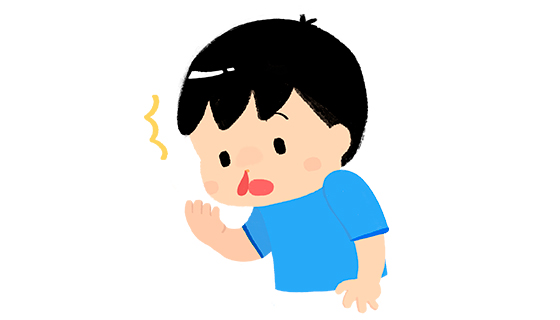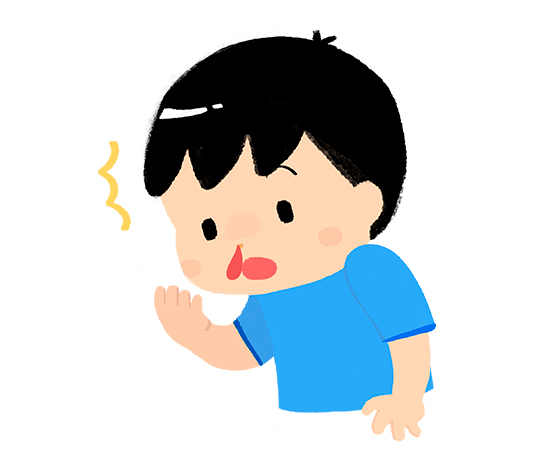mama知っ得!情報
溶連菌感染症ってどんなもの?

溶連菌は、溶血性連鎖(レンサ)球菌と呼ばれる細菌です。人に感染症を起こす溶連菌は、A群、B群、C群、G群などがありますが、溶連菌感染症の90%以上はA群です。そのため、一般的には『A群溶血性連鎖球菌』が原因の感染症のことを溶連菌感染症といいます。感染すると、主にのどの痛みや発熱(咽頭炎)、皮疹、舌に赤いブツブツ(イチゴ舌)が見られます。また、皮疹が強い場合には“しょう紅熱”、皮膚に感染した場合には“とびひ”、扁桃腺の深いところに感染すると“扁桃周囲膿瘍”など、さまざまな感染症状を引き起こします。稀に、急性期の症状が治った後にリウマチ熱(心臓を含む全身の炎症が起こる)や腎炎などの合併症を起こすこともあります。咳やくしゃみ、会話などで飛び散った菌を吸い込んだり、目や鼻などの粘膜につくことで感染します。多くは抗原検査で診断され、抗菌薬(原則10日間)と対症療法の服薬などの治療を行います。抗菌薬の投与を開始して24時間ほど経つと、他人にうつるリスクはなくなるといわれています。
溶連菌感染症の『気になるこんなこと』Q&A
Q1. 症状が治まっても、抗菌薬は全部飲み続けないといけない?
A.
咽頭炎の後にしばらくしてから、リウマチ熱や腎炎、肺炎、髄膜炎などの合併症が起こることがあり、それを予防するために10日間しっかりと抗菌薬を飲み切ることが大切です。そのため、症状が良くなっても途中で抗菌薬を止めてしまわないように注意しましょう。
Q2. 学校の出席停止の決まりはある?
A.
学校保健安全法では、第三種感染症の『条件によっては出席停止の措置が考えられる疾患』に区分されています。明確に出席停止期間の決まりはありませんが、全身状態が悪いなど病状によっては、医師が登校可能と判断するまでは出席停止が必要となる場合があります。登校・登園のタイミングについては、かかりつけ医へ相談しましょう。
Q3. 大人にもうつる病気?
A.
溶連菌感染症はどの年齢でも起こりうる感染症で、大人でもかかることがあります。ただし、人と接触する機会が多い場所で発生しやすい感染症のため、幼稚園や保育園、学校などの集団生活の中で子どもがかかることが多く、3歳以下の子や大人の症例は少数です。
Q4. 劇症型溶連菌感染症はなにが違う?
A.
報道では「人食いバクテリア」といって取り上られることもありますが、咽頭炎などの一般的な溶連菌感染症と、劇症型溶連菌感染症は、どちらも同じ菌が原因です。一般的な溶連菌感染症は子どもがなりやすいのに対し、劇症型溶連菌感染症は特に30歳以上の大人に多いという特徴があります。劇症型溶連菌感染症は、最初は腕や足の痛みや腫れ、発熱などの症状から始まることが多く、突発的に発症し、急速に呼吸の悪化や腎不全など全身に進行する重症感染症です。しかし、まだ感染経路や重症化に至るメカニズムは解明されていません。早期に適切な抗菌薬投与などの治療を開始することが重要なため、もし初期症状が見られた場合にはすぐに受診しましょう。
現在、溶連菌感染症のワクチンはありません。予防のためには、人混みを避けることや、マスク、うがい、手洗いなどの基本的な感染予防行動が大切です。溶連菌は、冬に流行りやすいなどの傾向はあるものの、年間通して起こりうる感染症ですので、帰宅後の手洗い・うがいなどを習慣づけていけるとよいですね。
東京海上日動メディカルサービス 発行
http://www.tokio-mednet.co.jp/