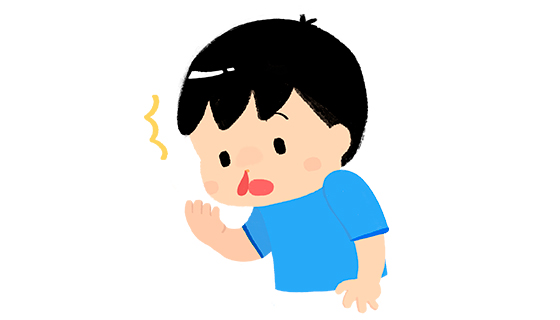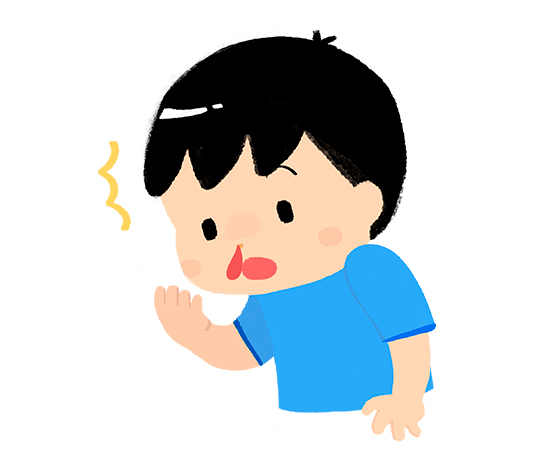mama知っ得!情報
「ひとりっこ」「きょうだいっこ」どんな関わり方が大切なの?

子どもが成長する過程で身についたらよいと思われる能力、大人になって必要とされる能力はどのようなものでしょうか。答えはいくつもありますが、例えば、自制心や共感力、他人との関係を踏まえたうえで行動する能力等々が含まれる『社会性』は必要な能力といえるでしょう。
子どもの『社会性』に関して、「子どもが集団生活で困らないようにしたい」、「お友達や兄弟との関わりにうまく対処できるようになって欲しい」など、期待することはたくさんありますよね。
この『社会性』を身につけるうえでその基盤となるものは、生まれてから保育者との関わりの間で形成される信頼関係である、と言われています。子どもの欲求やその時々の感情に反応した、適当な『保育者の応答』、この繰り返しが、子どもの安心感、共感力、信頼感として養われていきます。これらの信頼関係を基盤として、まわりの人や物ごとへも信頼がうまれ、『社会性』に繋がるものと考えられています。
「ひとりっこ」でも「きょうだいっこ」でも-保育者の関わり方-
「ひとりっこ」育児であれば、子どもは『保育者の応答』を頻繁に得て、社会性の基盤となる信頼関係を築き、また「きょうだいっこ」育児であれば、幼少期からの兄弟との当たり前の関わりや経験を通じて、子ども自身が『社会性』そのものを培う練習が進むと考えられています。
乳児~幼児期の子どもに対しての、適当な『保育者の応答』というのは、例えば、子どもが泣いている時、「どうしたの?おなかがすいたかな?」「ねむいかな?」「暑いのかな?」というように、保育者が子どもの行動や状況から子どもの感情を推察し、その感情に対して意識的に応答するということです。「きょうだいっこ」の日常的な衝突の際にも、子どもが言葉として表現しきれない感情を、保育者が代弁するように言葉にすることで、子どもの感情の高ぶりが落ち着くことなどはよくみられるものです。加えて、子ども自身がどのように相手に自分の要求を伝えたらよいか、状況をおさめるための言葉がけ、関係を変えるための提案の言葉など、時には保育者がタイミングを見ながら声掛けをするということも、子どもが他人との関わり方を学ぶよい機会になります。
「ひとりで抱え込まないこと」を大切に
厚生労働省の「国民生活基礎調査(2022年)」によれば、18歳未満の子のいる世帯、かつ母親が仕事をしている割合は75.7%となり、働きながら育児をする女性が増えていることが確認されています。主として育児に携わる女性は、限られた時間のなかでの育児と仕事の両立に奔走していることでしょう。そのような多忙な生活のなかでの育児となれば、子どものアクションにじっくり関わることの難しさ、適切なタイミングでの応答の難しさだけでなく、まわりの人の状況もわからない!等のストレスにもなってしまいます。
一方でこの『社会性』とは、子どもと保育者との関わりに限定されず、生活の多様な場において、多くの人との関わりを通じて、学習的に身についていくものでもあることもわかっています。であれば、育児をひとり抱え込まないことは、保育者のメンタルヘルスケアとしても役立つだけに留まらず、子どもが社会との関わりのなか『社会性』を育くむ機会を増やすということになります。保育者の方は、時にストレスにもなる育児をひとりで抱え込まないよう、社会資源や周囲の協力が得られる育児環境を整えることも大切にしていきましょう。
東京海上日動メディカルサービス 発行
http://www.tokio-mednet.co.jp/