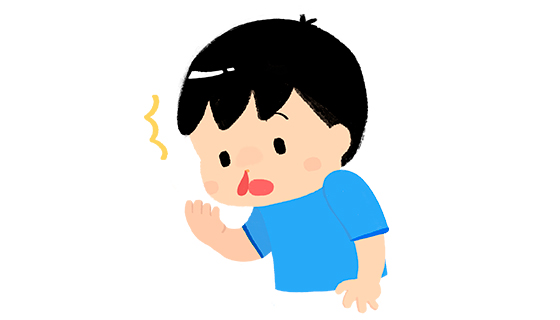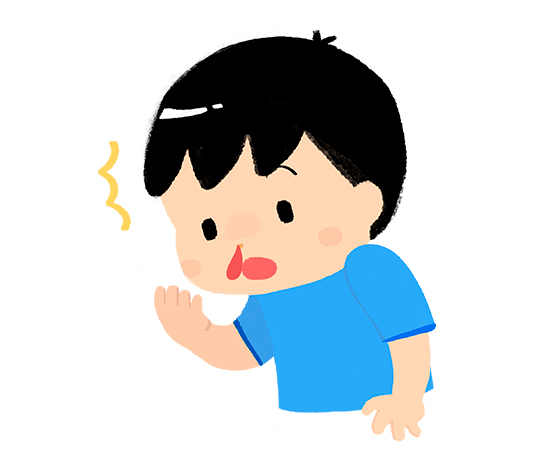mama知っ得!情報
メタボ体型を改善したい!テレワークでも減量できる方法を教えてください。

メタボリックシンドロームとは?
メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪型肥満(※)に高血圧・高血糖・脂質代謝異常が組み合わさることにより、心臓病や脳卒中などになりやすい病態のことです。日本でのメタボリックシンドロームの診断基準では、「ウエスト周囲径(へその高さでの腹囲)が男性85cm・女性90cm以上」かつ「血圧・血糖・脂質の3つのうち2つ以上が基準値外」のとき、メタボリックシンドロームと診断されます。
※内臓脂肪型肥満:内臓周辺への脂肪蓄積が目立つ肥満のこと。内臓脂肪型肥満と診断されるのはCT検査などで内臓脂肪の面積が100㎠以上のとき。ただし一般的には、内臓脂肪面積100㎠の状態をウエストサイズに換算した平均値が用いられ、ウエストサイズが男性85cm以上・女性 90cm以上を内臓脂肪型肥満とする。
近年、脂肪細胞は体の中でいろいろな化学物質を作ることがわかってきています。その化学物質の多くは良くない働きをすることが明らかになっています。たとえば、糖尿病になりやすくする・動脈硬化を促進させる・血圧を上げるなどの作用をもたらすのです。
 (厚労省e-ヘルスネット)
(厚労省e-ヘルスネット)
メタボ体型からの減量ポイント
①食事はよく噛んで食べる/1日3食、できるだけ決まった時間に食べる
食べはじめてから満腹を感じるまでには20分程かかるといわれています。早食いが肥満を助長するのは、満腹を感じるまでに勢いよくたくさん食べてしまうことで、つい食べ過ぎてしまうからです。よく噛んでゆっくりと食べることによって、食事の時間が長くなって満足感が増し、食べすぎの予防になるばかりでなく、消化を促し胃腸の負担も少なくできます。
また、食事の間隔が長くなりおなかが空きすぎてしまっていると、つい早食いになり食べ過ぎてしまう傾向があります。できるだけ毎日決まった時間に食事をとるようにしましょう。
②夜間の飲食量を軽めにする
夕食を食べてから寝るまでの時間が短いとエネルギーが消費されず、血液中に余った栄養は脂肪に変えて蓄積されます。これが内臓脂肪のもとです。就寝時には、満腹よりもおなかが空いたなあと感じるくらいがよいでしょう。夕食の量は普段の8割程度に控え、夕食後の飲食は極力しないようにしましょう。仕事などで夕食が遅くなってしまう場合は、エネルギーを抑えた消化のよい食事がおすすめです。
③過度な飲酒に注意しアルコールは適量にする
少量の食前酒は食欲を促す作用がありますが、多すぎてはいけません。肥満はお酒自体のカロリーだけでなく、一緒に食べるおつまみが脂っこいものだったり、アルコールで食欲が亢進したりすることでも起こるといわれます。飲みすぎには注意し(適量は1日/日本酒なら1合、ビールは500mL、焼酎は0.6合程度)、おつまみは低エネルギーで高たんぱくな枝豆や冷奴(湯豆腐)、お刺身などにするとよいでしょう。
④ダイエットは長期的に継続する
無理なダイエットは継続できないばかりか、体に負担が多く、筋肉が落ち、かえって脂肪が増えるリスクがあります。たとえば「〇〇抜きダイエット」などで食事のエネルギー量を極端に減らせば短期的に痩せることができても、急激な減量は体が危険を感じて食欲を増進させ、リバウンドに繋がったりします。バランスのよい食事で過剰な総摂取エネルギーを減らし、長期的に無理なく続けられることが大切です。
⑤ストレスは運動や体を使った趣味で発散する
食事をすることでストレスを発散させるという方も多いですが、せっかくならばウォーキングやジョギング、ゴルフの素振り、カラオケなど、体を使って解消するのがお勧めです。適度な運動によるストレス解消効果+エネルギー消費となり、ダイエットには効果的です。
まずは今の生活の中でできるところから食生活改善や運動習慣獲得をし始めて、無理せず長く続けるやり方で、メタボ体型の改善、そして健康的な生活習慣を手に入れていきましょう。
東京海上日動メディカルサービス 発行
http://www.tokio-mednet.co.jp/