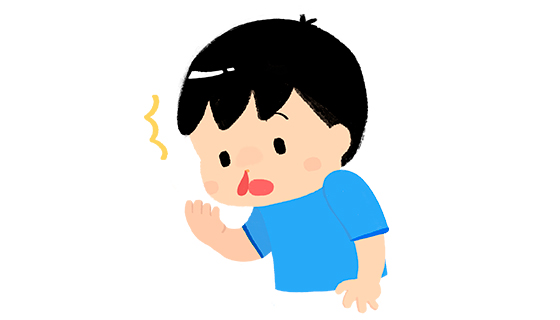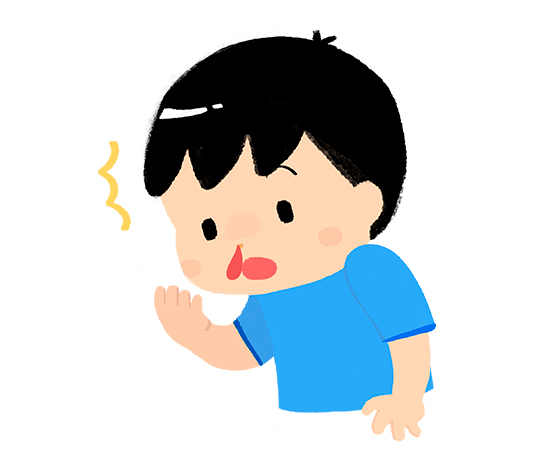mama知っ得!情報
子育ても仕事も楽しみたい! 「子連れワーケーション」の魅力とは?

最近よく聞くようになった「ワーケーション」という言葉。これは「ワーク」と「バケーション」を合わせた造語で、その名の通り旅先などで休暇を楽しみながら働くことです。日本では、コロナ禍でリモートワークが普及した2020年以降に注目を集めるようになりました。
働く場所を厳しく制限せず、好きな時に、好きな場所に行って仕事をする。そんなワーケーションのスタイルは、実は子育て世代にこそうってつけ! 今回は、自分自身が子連れワーケーションの魅力に引き込まれ、その普及を目指して「親子ワーケーション」事業を手がけている児玉 真悠子さんにインタビュー。子連れワーケーションの魅力やおすすめのワーケーション先などを伺いました。

2021年の春には沖縄でのワーケーションを体験。「花粉症の私にとって すぎ花粉ゼロの沖縄は快適でした」と児玉さん。
(写真提供:児玉 真悠子)
ワーケーション体験から見えてきた、子どもたちの可能性
——子連れワーケーションを始めたきっかけからお聞かせください。
児玉:もともとはフリーランスの編集者・ライターとして働いていたのですが、2019年の夏に、山口県萩市から「ワーケーションをテーマに、萩市の魅力をPRするパンフレットを作ってほしい」という依頼があったんです。
実際に10日間ほど萩市に滞在して、地域の魅力やワーケーションのノウハウなどをパンフレットにまとめるというお仕事でした。
とはいえ、当時の私はフリーランスではあるものの、夫が会社勤めで残業や出張も多く、小学5年生の息子と1年生の娘をワンオペで育てているような状況でした。それで、「夏休みに子連れなら行けます」とお伝えしたところ、萩市のご担当者が「ぜひ、お子様連れでの体験もパンフレットに盛り込んでください!」と快諾してくださったのです。

初めての子連れワーケーションで訪れた山口県萩市。市内には、江戸時代の文化史跡が多く残っている。
(写真提供:児玉 真悠子)

笠山の自然体験ツアーに参加した子どもたちは、約2万5000本のヤブツバキが自生する群生林を見学。
(写真提供:児玉 真悠子)
——その体験を通じて、ワーケーションの可能性や楽しさを実感したわけですね
児玉:その通りです。萩市にいる間は、重要文化財の古民家を改装した移住体験用の住宅に滞在させてもらったのですが、3DKの広々とした住宅内にはサテライトオフィスとして使える個室があって、Wi-Fiも完備。仕事をするのに十分な環境でした。何より歩いて10分で海に行ける環境に子どもたちは大喜び!
朝は早起きしてそれぞれに仕事や宿題をし、お昼ごはんを食べてからは海水浴に行き、その後は周遊バスで図書館や博物館を巡るといった具合で、有意義な毎日を過ごすことができました。
ゲームをしたりテレビを見たり、自宅でだらだら過ごすのと違って、子どもたちが本当にいきいきと楽しそうで、こんな休暇の過ごし方もありだなと感じましたね。同時に、少子高齢化が深刻な地域に子連れワーケーションで訪れることは、地域にとっても賑わいにつながることを実感。地域にも親にも子どもにも「三方良し」だと感じました。

宿の軒先では、みんなでスイカ割りを体験。東京の自宅ではなかなかできない体験に、子どもたちは大満足!
(写真提供:児玉 真悠子)

図書館に隣接された児童館内のスペース。すきま時間を活用してメールチェックをする児玉さん。
(写真提供:児玉 真悠子)
——実際に体験してみてわかった、ワーケーションの魅力やメリットは何でしょう?
児玉:「暮らすように滞在する」というのがワーケーションの特徴ですが、環境が変わって気持ちがリフレッシュできるので、東京にいる時よりもメリハリを持って働けるように感じます。滞在中は宿のキッチンで自炊することもあるのですが、鮮度抜群のお魚や珍しい食材など、地元グルメを堪能できるのもうれしいポイントですね。
——仕事をして、休憩を取るために外に出てみると、そこはいつもと違った非日常の世界が広がっている。想像するだけで、とても新鮮な体験だとわかります
児玉:その土地ならではの子ども向けアクティビティに参加することで、子どもたちの「意外な興味や特技」を見つけてあげられるのも、ワーケーションのメリットだと感じます。
たとえば、娘は森や川などの自然が大好きで、新潟県湯沢町に行った時には、地元の子たちよりも上手に魚を捕まえて、うれしそうに見せてくれました。そんな特技が娘にあったなんて私もびっくりしましたし、都会で暮らしているだけではなかなか気づけなかったと思います。一方の息子は、道を覚えるのが得意。はじめて訪れた土地でも、方向音痴の私を目的地まで連れて行ってくれます。
もちろん、旅行をするだけでも似たような経験はできると思いますが、私の場合は子連れワーケーションという働き方を取り入れ、一緒に出かける頻度が増えたことが、そうした発見につながっています。地元で遊ぶこと以外の選択肢ができるのは、子どもにとっても親にとっても、本当に大事なことですよね。

糸魚川市・柵口の万年雪での雪遊び風景。子どもたちは「夏なのになぜ雪があるの?」と不思議がっていたそう。
(写真提供:児玉 真悠子)

湯沢町で行われた魚のつかみ取り体験では、娘さんが意外な才能を発揮しました。
(写真提供:児玉 真悠子)
——子連れワーケーションには、たくさんのメリットがあるんですね。
児玉:私自身、親として子どもたちの職業選択の幅を広げたいと考えているので、たくさんの場所に出かけて、いろいろな人、いろいろな仕事、いろいろな日常があることを、子どもたちに知ってもらえるのも、ワーケーションの良さだと思っています。
そして何より、「せっかくの夏休みなのに、ずっと保育園ばかりで申し訳ないな」「今、生き物に興味を示しているから、もっと見せてあげたいのに、そういう場所に連れて行けてないな」という罪悪感を払拭できたのが、とても大きなメリットでした。
子連れワーケーションの受け入れに積極的な自治体が増えてきた!
——特に印象に残っているワーケーション先はありますか?
児玉:長崎県五島市の福江島で、子どもたちは現地の小学校に短期体験入学し、私は滞在先で普段通りに仕事をする、というワーケーションを経験したことです。最初はガチガチに緊張していた子どもたちが、お別れの日には涙目になるほど仲良くなっていて、私自身とても感動したのを覚えています。「牛乳が瓶じゃなくて紙パックだった」とか「給食の後にみんなで歯みがきしたよ」「給食で鯨のお肉が出たよ」など、東京の学校との違いを見つけるたびに、楽しそうに教えてくれたのも印象的でしたね。
他にも、日本で初めてジオパークに認定された新潟県の糸魚川市や同じ新潟県の湯沢町、福岡県福津市なども、自然に恵まれていてとても魅力的なワーケーション先でした。
加えて、最近は子どもたちの興味に合わせてワーケーションを楽しむことも増えましたね。「日本の三大都市を制覇したい」という息子のリクエストに応えて名古屋に行ったり、コロナ禍で中止になってしまった修学旅行先の京都を訪ねたりと、フットワーク軽くいろいろなところに出かけています。

五島市立福江小学校に1週間の体験入学。自治体主導のワーケーション企画だと、こうした貴重な経験もできます。
(写真提供:児玉 真悠子)

五島列島の福江島までは、長崎空港からプロペラ機で約30分の道のり。初めてのプロペラ機に子どもたちは大喜び!
(写真提供:児玉 真悠子)
――ワーケーション先を選ぶ際のポイントについても教えてください。
児玉:自分が行ってみたいところだったり、子どもの興味に合わせたりして選ぶのが良いと思います。最近では、親子ワーケーションの推進に力を入れている自治体も増えているので、そうした地域から選ぶのもおすすめです。
なかでも、私が先に挙げた糸魚川市や湯沢町。そして鳥取県や徳島県、栃木県那珂川町、北海道厚沢部町などは、親子ワーケーションの受け入れに積極的で、小学校や保育園の短期入学制度を設けたり、民間事業者が長期休暇中に日中のお預かりをしてくれる民間学童のようなプログラムを設けたりと、子どもが預けられる場を作ってくださっています。もちろん、他の地域でも各自治体が親子ワーケーションツアーなどを企画していたりするので、興味のある自治体の公式サイトやSNSなどをこまめにチェックしてみてください。

栃木県那珂川町でも体験入学に参加。「ようこそ馬頭東小へ」と書かれた手づくりの飾りで歓迎を受けました。
(写真提供:児玉 真悠子)

栃木県那珂川町でのひとコマ。子どもたちは地元の方に教わりながら竹細工の製作に挑戦!
(写真提供:児玉 真悠子)
——「子連れワーケーションに興味はあるけれど、ハードルが高い」と感じている方も多そうです。
児玉:そうした方には、移動時間や交通費がなるべくかからない場所を選んで、お試しの子連れワーケーションを実践してみるのがおすすめです。たとえば、お休みの日に家族で近場の日帰り温泉のような施設に行って、そこでパパとママが子どもたちの相手と仕事を交代でやってみる。あるいは、近場のコワーキングスペースや仕事がしやすいカフェの近くにある公園に行って、パパとママで交代しながらワーケーション的な過ごし方をしてみる。そうやってお試しをしてみると、どんな場所なら仕事をしやすいか、どんな条件ならリフレッシュできるかが分かってきます。
また、会社勤めだと、平日に会社の許可を取ってワーケーションを行うのが難しい人が多いと思います。その場合は、ワーケーションをリモートワークの延長だと捉えて、半日だけ旅先で働くことができるかを相談してみてはいかがでしょうか。遠方の実家でのワーケーションなら許可しているという会社もありますので、実家から始めてみるのも、ハードルが低くておすすめです。
——ワーケーションを行うにあたっての注意点はありますか?
児玉:ワーケーションはバケーションではないので、宿泊やレジャーなどに予算をかけすぎない方が満足度が高くなりやすいでしょう。私も、1週間以上滞在する場合は専門サイトで民泊を探したり、宿泊料金が月額固定の全国泊まり放題のサブスクリプションを利用するなど、滞在費を抑えるようにしています。キッチンや洗濯機などが付いた物件だと、費用だけでなく持ち物も減らせて一石二鳥ですよ。

ワーケーションでは、遊びと仕事を交互に取り入れ、メリハリを持って過ごすのがコツ。
「午後遊ぶために、子どもたちは午前中に集中して宿題を終わらせていました」と児玉さん
(写真提供:児玉 真悠子)
——最後に、この記事を読んで子連れワーケーションに興味を持たれた読者のみなさんに向けて、メッセージをお願いします。
児玉:私自身も長く共働きで子育てをしてきましたが、「子どもの好奇心に合わせた体験をさせてあげられていないのでは?」「仕事をしているせいで、子どもの成長機会を奪ってしまっているのでは?」という葛藤を抱えながら過ごしていました。仕事と子育てがトレードオフの関係に思えていたんです。でも、子連れワーケーションという解決策に出合ったことで、その葛藤は吹き飛びました。ですから、子連れワーケーションが今後普及すれば、自分らしく子育てをすることも、働き続けることもどちらもあきらめない生き方が実現できるはず。そういう意味で子連れワーケーションは、共働きしやすい社会に必要なインフラのようなものかもしれません。
とはいえ、ワーケーションは行く側にとっても、受け入れる側にとってもまだ試験期間のような段階。「うまくやらなきゃ」と構えずに、まずは気軽に楽しんでみてはいかがでしょうか。

児玉 真悠子/株式会社ソトエ代表取締役、一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・ フリーランス協会 地方創生チーム&フリパラ編集部、一般社団法人日本ワーケーション協会公認ワーケーションコンシェルジュ
ビジネス系出版社を経て、2014年にフリーランスの編集&ライターとして独立。現在、「親子ワーケーション」を普及すべく邁進中。
親子deワーケーション
https://www.oyakodeworkation.com/