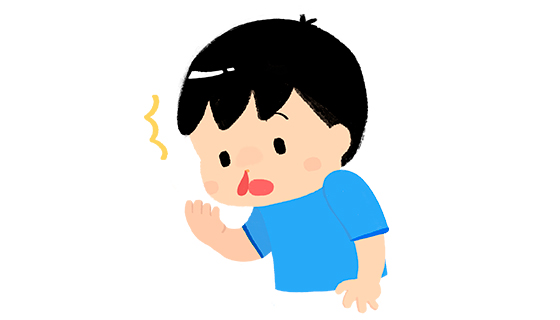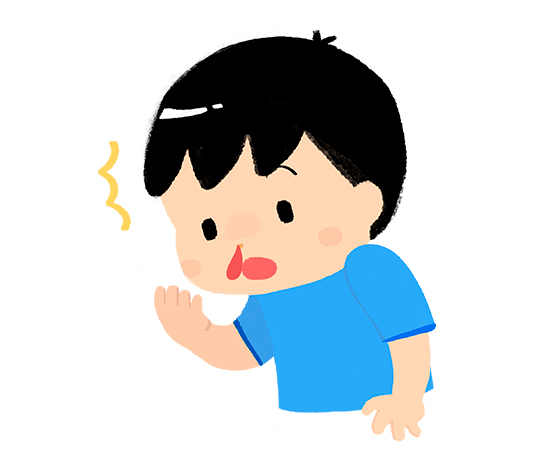mama知っ得!情報
ママFPに聞く、子ども名義の口座は必要?

みなさんは、お年玉やお祝い金など、子どもがもらったお金の管理をどうしていますか? 方法の1つとしてあげられるのは、子ども名義の預金口座を開設する方法です。子ども名義の預金口座があると、子どものお金と生活費とをきちんと分けて管理できるうえに、子どものマネー教育にもなります。そこで今回は、子ども名義の預金口座の作り方や活用法、注意点などをママであり、ファイナンシャルプランナーの高山一恵さんにレクチャーしていただきました!
子どもの口座を開くために準備するものは?
銀行口座は、戸籍謄本がある方なら誰でも開設可能です。子ども名義の口座は保護者が代理で手続きをすることができ、窓口に本人を連れていく必要もありません。
準備する書類は下記が一般的ですが、金融機関ごとに指定される書類が異なるので、実際に開設するときには事前に確認しましょう。
□子どもの本人確認書類(住民票、健康保険証、マイナンバーカードなど)
□親権者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
□親権者であることが確認できる書類(戸籍謄本、住民票、健康保険証、母子手帳など)
□届け出印(銀行印)
子どもの口座はどのように使うのがいい?
子ども名義の口座の活用法は、大きく2つに分けられます。
1つ目は「貯蓄」です。お年玉、お祝い金、お小遣いなどを貯金するほか、児童手当を子ども名義の口座に振り分けて貯めている家庭もあります。児童手当を全額積み立てれば、15歳までに約200万円を貯蓄できるため、大学進学の費用にあてたり、お子さんが成人したときに渡してあげたりといった使い方もできますね。
また、「夫婦で毎月決まった額を入金し、教育資金を積み立てる口座として活用している」という声も聞かれます。貯蓄を目的とする場合は、乳幼児期に口座を開設し、時間をかけてコツコツと貯めていくのがおすすめです。
2つ目は「マネー教育」です。「口座にお金を入れると貯まる」「欲しいものを買うと減る」といったことをダイレクトに体感するのは、子どもにとって大切な経験です。とくにキャッシュレス決済が浸透しつつある現代では、「お金は使うと減る」という当たり前のことが実感しにくくなっており、「カードをかざせばなんでも買える」「足りなければチャージすればOK!」と勘違いしている子もいます。通帳には、お金の出入りが実感しやすい数字で残るので、親子で管理することで、金銭感覚の土台が身に付いていくでしょう。
マネー教育が目的であれば、口座開設は子どもがお金について興味を持ち始めてからで十分です。「自分のお小遣いで欲しいものがある」「今までもらったお年玉はいくらある?」など、お金に関することが話題にのぼるようになったら、検討してみるといいでしょう。
子ども口座を使って「マネー教育」を始めましょう
ご存じのように、近年マネー教育の重要性が叫ばれるようになりました。2022年4月からは、高校の家庭科で金融教育の授業もスタートしています。今後、金融教育が始まる年齢は、さらに低年齢化すると考えられ、幼少の頃からお金のことを学ぶ機会が増えていくでしょう。
かつて、日本の経済が右肩上がりで成長していた時代は、「年齢が上がれば給料も増える」ことを前提に人生プランを立てることができました。ところが、低成長が続く現代では、年齢が上がったからといって自動的に収入も上がるとは言い切れません。企業の福利厚生の縮小や、年金や退職金が目減りするといった状況が予想されるなか、資産運用でお金を増やす自助努力が求められるようにもなりました。
また、若い世代では、キャッシングやゲームへの過度な課金など、お金のトラブルも増えています。だからこそ、家計管理、消費者教育、投資教育の3本柱は、これからの社会を生きる若い世代にとって欠かせない知識であり、スキルだと言えるでしょう。
そうしたなか、教科書で学ぶだけでなく実際に自分の口座を持ち、お金を貯めたり、使ったりする経験を積むことは、将来の自立につながるステップとなります。「子どもにまとまったお金の管理を任せたり、自由に使える状態にするのは不安」と感じる方もいるかもしれません。あるいは「無駄遣いをしてしまわないか、心配」といった親心が働くケースもあるでしょう。しかし、長い人生においては失敗から学ぶことが多いのも事実。親子で一緒に管理するやり方をベースにしつつも、子どもが「自分のお金を使いたい」という時にはできるだけ口を出さずに見守ってあげたいものです。
そして、折に触れてお小遣いをどう使っているか、貯金ができたら何をしたいか、普段通っている習い事や塾には毎月いくらかかっているのかなど、親子でお金について話す機会を作っていけるといいですね。
子ども口座の一部資金で投資にチャレンジ!
お金や社会への関心が高まってきたら、子ども口座に入れたお金の一部で、投資にチャレンジしてみるのもおすすめです。
株式投資の場合は1株から購入できるものもあり、少額で気軽に始められるのが魅力です。「人気アニメのコラボグッズがたくさん売られているから、グッズを作っているおもちゃメーカーは好調かも」「映画がヒットしたから、映画会社がもうかっているんじゃない?」など、身近な気付きから経済の仕組みに興味を持つきっかけにもなるでしょう。実際に株式を買わなくても、親子で銘柄を選んでシミュレーションしてみるのも楽しいですよ。
株式投資を始めるには、証券会社に口座を開く必要がありますが、子ども名義でも口座を開くことができます。ご興味のある方は、証券会社に問い合わせてみてくださいね。
また、東京証券取引所のキッズ向けワークショップなどに参加してみるのもいいでしょう。 ニュースでよく見る証券取引の様子を見学できたり、投資の仕組みをわかりやすく学べたりと、親子で楽しくお金について学ぶことができます。
子ども口座開設で注意するべきポイントは?
さまざまなメリットがある子ども口座の開設ですが、いくつか注意しなければならない点もあります。
●贈与とみなされる場合がある
子ども名義であっても、実質的な入出金の管理を親が行っている場合には、贈与とみなされる可能性があります。そして、贈与と判断されると年間110万円を超えた分について、贈与税がかかります。
対策として、入金を年間110万円以内に抑えるか、子ども自身が管理する形を整えるかの2つあげられます。本人の銀行印を作り、通帳の管理も子どもが主体的にしていれば問題ありません。また、教育費に使用する場合は、1500万円まで贈与税の非課税制度が適用されます。ただし、子ども自身が管理する場合でも、貯金額やお金の使い方については親子で共有することが大事です。
●休眠口座にならないように注意!
「貯蓄目的で子ども口座を開いたものの、結局、親の口座で貯めていくほうがスムーズだった」などの理由から、子どもの口座が活用されないケースもあります。10年間取引が行われない場合、その口座は休眠口座となり、保有している預貯金は民間公益活動に利用されます(10年間取引のない預金は、休眠預金と呼ばれます)。金融機関で手続きをすれば預金を引き出すことはできますが、ATMではなく窓口での手続きが必要です。口座を開設した際は忘れずに管理をし、休眠預金にならないように注意しましょう。
●1つの銀行に持てる口座は1つだけ!
例えば、子どもが成長してアルバイトを始めたとき、アルバイト先から「給与振込はA銀行」と指定されることがあるかもしれません。しかし、すでにA銀行に子ども名義の口座がある場合は、新しく口座を作ることはできません。
子どもの口座を「貯蓄用」として活用している場合、子どもが自由に使えるアルバイト料の振込と貯金とは分けておきたいもの。その場合は、別の銀行に貯蓄用口座を作り、これまでの貯蓄分を移すなどの工夫が必要となります。
●成人後は、親でも勝手に引き出せない
18歳以降は、名義人本人でなければ預金の引き出しはできません。たとえ大学の授業料を貯めるために貯蓄をしていたとしても、親が勝手に引き出すことはできなくなります。
夫婦や親子で「口座開設」の目的を話し合いましょう
前述したように、貯蓄を目的にするのか、マネー教育を目的にするのかで、子ども名義の口座を作るタイミング、管理の仕方なども変わります。まずは夫婦でよく話し合い、「わが家の子ども口座活用法」を検討してみましょう。お子さんがお金について興味を持つ年齢になっていれば、お子さんを交えた家族会議の議題とするのもいいですね。

高山一恵/ファイナンシャルプランナー
慶應義塾大学卒業後、2005年に女性のためのファイナンシャルプラニングオフィス、株式会社エフピーウーマンの設立に参画し、取締役を務める。15年に株式会社Money&Youの取締役へ。相談業務のほか、講演、執筆などでも幅広く活躍。わかりやすい解説に定評がある。『1日1分読むだけで身につくお金大全』など著書多数。