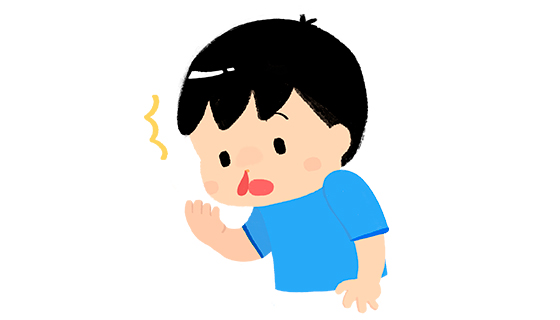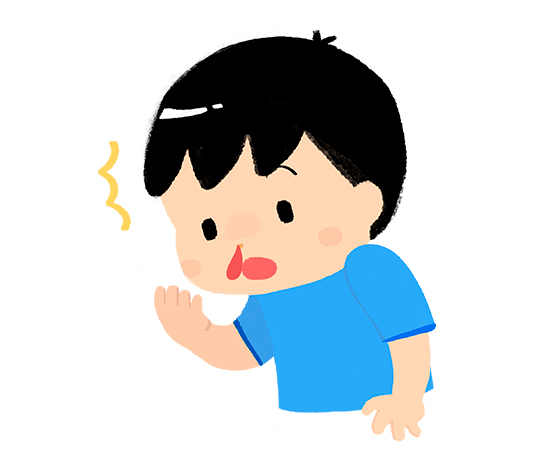mama知っ得!情報
「パパ育休」のリアルを経験者に聞きました!産後パパ育休制度スタート!

育児・介護休業法が改正され、2022年10月1日に 「産後パパ育休(出生時育児休業)」 という新しい制度が施行されました。
従来の育休制度に加え、子の出生後8週間以内に
4週間の育休が小分けで取得できるようになり、パパの育児参加へのハードルがこれまで以上に下がることが期待されています。
「産休=ママのもの」という考え方が過去のものになりつつある今、2019年に2カ月の育休を取得し、「note」などを通して夫婦の育児分担に対する提言を行っている 前田晃平さん (内閣官房こども家庭庁設立準備室参事官補佐) に、「パパ育休」のリアルや意義についてうかがいました。
育休前に購入していた本は 1冊も読めなかった
――育休を取られた理由を教えてください!
前職が「親子の笑顔をさまたげる社会問題を解決する」というミッションを掲げるNPO法人だったので、
育休を取得しないという選択肢は最初からありませんでした。
――育休は最大で1年間の取得が可能です。2カ月間という期間はどのようにして決められたんですか?
1カ月では短すぎるだろうし、子どもが生まれたのが10月末だったので、年明けから復帰ぐらいでちょうどいいかなと。
妻も「それくらいでいいんじゃない」と同意していました。
――育休に入る前に準備したことがあったら教えていただけますか?
今振り返ると本当にお恥ずかしい話ですが、「育休生活をどうエンジョイするか」という準備が主でした(笑)。
2カ月間も大人2人がかりですし、妻の実家が近いので祖父母の支援も得られる。
控えめに言って恵まれているし余裕もあると考えていたので、休暇中に読むための本をたくさん購入して、
「まあなんとかなるだろう」という状態で育休に突入したんです。蓋を開けてみたら本なんて1冊も読めませんでしたけど(笑)。
――考え方を改めなければと思ったのはどのタイミングでしたか?
子どもが生まれてすぐですね。
うちの子は夜にまったく寝なかったんです。
寝ても2〜3時間くらいだし、起きているときの機嫌は基本的に最悪。妻の産後の体調もよくなかったので、「これは自分がいないとやばいな」と、すぐに思いました。
――育児や家事のタスク分けはどのようにされていましたか?
きっちりと分担していたわけではないのですが、
授乳や肌のケア、育児に関する調べ物などは妻がやり、掃除や皿洗い、買い物やお風呂などは、私がやることが多かったです。夜間のミルク作りは私の分担にはなっていましたが、妻も結局起きちゃって、2人とも寝不足でフラフラ。奇跡的に娘がまとまって寝たときも、自分のことをやろうなんてまったく考えられず、ひたすら寝ていました。
育休を経て、妻は「運命共同体」になった
――新生児の育児について、誕生前の想像と違ったことはありましたか?
やっぱり子どもが寝なかったことですかね。
抱っこでウトウトしたところを布団に下ろしたら泣き出すという流れを何度も繰り返すのは本当にきつかったです。
電動のバウンサーや赤ちゃんが安心すると言われているおくるみなど、いろいろなグッズも試したけれど
うちの子にはどれも合わず、いつも「名探偵コナンの麻酔銃が使えればいいのに」と思っていました(笑)。
4人兄弟の長男で弟たちの世話をよくしていたこともあって、その他の作業はイメージ通りではあったんですが、それが複合的に押し寄せてきたときに処理できなくなる感じや、「自分たちがちゃんとしなかったらこの子は死んじゃうかもしれない」みたいな責任と覚悟の重さは想像以上のものでした。

娘さんの爪を切る前田さん。慣れるまでは怖い作業だが、苦なく行えたという。
(写真提供:前田 晃平 氏)
――育休が終わったとき、率直にどんな感想でしたか?
妻を残してきたことへの罪悪感と、「助かった!」という開放感の両方です。
「うわ、仕事って楽!」って思いました。
大人は話が通じますし、みんな合理的に優しくふるまってくれますし(笑)。
――パパの育休は、ママの負担を軽減するという点はもちろんですが、
子育ての大変さが実感できるという点でも、すごく意味のあることだと思います。
そうですね。それを理解しているかしていないかで、その後の夫婦の関係性やコミュニケーションも変わってくると思います。よくドラマやマンガで、仕事から帰ってきた夫が「俺だって仕事で疲れてるんだ」みたいなことを言いますけど、一体どっちが疲れているか、育休を取ればわかると思います。そういう意味でも男性は絶対に育休を取ったほうがいいと思います。
――前田夫婦の場合、育休取得前と取得後で関係性はどう変化しましたか?
子どもが生まれる前は、どちらかというと独立した関係でしたが、産後直後からともに育児をしてきたことで、「運命共同体」というか、お互いに背中を預け合っているパートナーみたいな関係になれたと思います。お互いに感謝の言葉をよく口にするようになりましたし、 “子はかすがい”ということわざは本当なんだなって思いました。
自分にしかできない役割が家庭にはある

育休明け以降は忙しい日々を送っているが、奥さんと協力しながら育児をしている。
(写真提供:前田 晃平 氏)
――キャリアのことなどを考え、育休を取ることに抵抗を感じる方もいらっしゃると思います。妻側から「育休を取ってほしい」と夫に働きかけるとしたら、どのようなアプローチが効果的でしょうか?
最初のお子さんの場合はピンときづらいと思いますが、産褥期がいかに危険な期間かということはご主人にきちんと知らせたほうがいいと思います。体のあちこちが傷つき、ホルモンバランスは乱れ、夜は眠れない…。妊産婦の死因の1位は自殺です。
本当に命に関わる時期だということをきちんと伝えたら、ご主人も真剣に取得を検討してくれるのではないかと思います。
あとは「育休を取ってくれたら、とてもうれしい」という気持ちも伝えたほうがいいと思います。
男性というものは、えてして「長く働いて出世して奥さんに喜んでもらおう」なんて考えがちなんですけど、「そんなことよりもそばにいてほしい」と伝えたら、「え、そうなの?」って思う人もそれなりにいると思います。
ただ、現状は残念ながら男性のキャリアにリスクがつきまとうので、女性も考え方を変えなければいけない。
奥さんが「大黒柱は1本でなく2本」という意識を持って伝えれば 、ご主人も育休を取りやすくなるんじゃないかと思います。
――最後に、育休パパの先輩として、後輩たちにメッセージをお願いします。
私はもともと「イクメン」なんてタイプではまったくなくて、育休を取ったことで初めて考え方が変わったタイプです。民間企業に勤めていた身としては、育休取得がいかにハードルが高いことで、取りたいけれど取れたら苦労しないよという人がいかにたくさんいるのもわかります。ただ、人生の中で本当に大切なものが何かというのを、我が子の誕生という機会に胸に手を当てて考えてみてはいかがでしょう。
ぶっちゃけた話、1人が数カ月仕事を抜けたところでたいていの組織は回りますし、社会に対して自分しかできないことなんてそうそうない。
しかし、 家庭にはそれがありますし、奥さんが文字通り命の危機に直面している期間に1人ぼっちにしておくことが本望なのかということは、よくよく考えてみてほしいです。
10月から始まった「産後パパ育休」は、育休は取りたいけれど…と思っている方の背中を押す制度です。数カ月はハードルが高くても、数週間だったら職場の理解も得られやすいと思いますし、何より、その数週間は奥さんとお子さん、そしてあなたにとって、とても重要な期間になると思います。ぜひ勇気を持って、制度を利用してもらいたいと思います。

前田 晃平 (まえだ・こうへい)
1983年生まれ。慶應義塾大学総合政策学部を中退後、株式会社リクルートホールディングス、NPO法人フローレンスを経て、内閣官房こども家庭庁設立準備室参事官補佐に。政府「こども政策の推進に係る有識者会議」メンバー。
著書に『パパの家庭進出がニッポンを変えるのだ!』(光文社)。
noteはこちら: https://note.com/cohee/