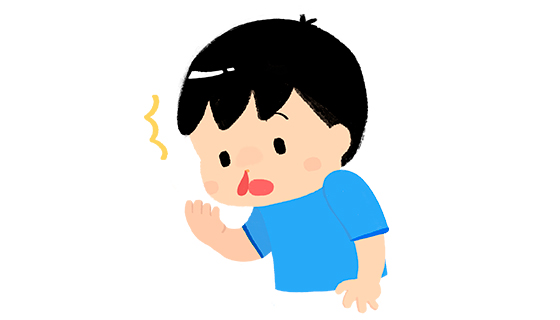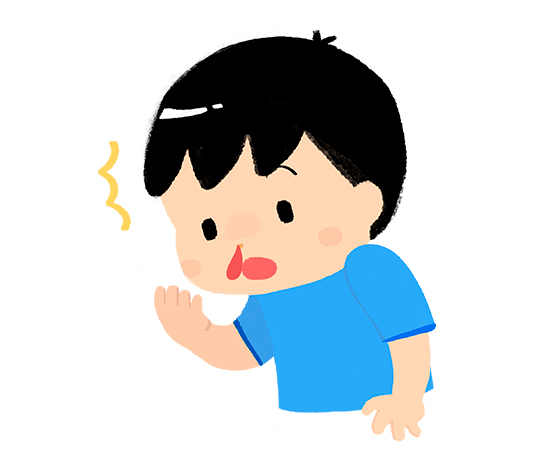mama知っ得!情報
子どもが楽器に親しむためのファーストステップは? 楽器の「はじめどき」を知りたい!

手遊び歌や童謡、おもちゃから流れるメロディなど、赤ちゃんの毎日はさまざまな「音楽」で彩られています。でも、楽器演奏を身につけさせようと思うと、途端にハードルが高く感じられて、いつ頃、何から与えるべきか迷ってしまうママ&パパも多いかもしれません。
リトミック国際サティフィケイトの資格を持ち、多くの子どもたちを指導するNPO法人日本こども教育センター代表の井上幸子さんに、乳幼児期の楽器との関わり方についてうかがいました。
子どもが楽器遊びをするメリットとは?

◎集中力がつく
音楽に合わせておもちゃの楽器を叩いたり、振ったりしているとき、大人からするとただ好き勝手に手を振り回しているように見える子どもも、実は集中力を研ぎ澄ませています。高い音、低い音、ゆったりしたリズム、アップテンポ、明るい曲調、悲しい曲調…そうしたことを全部感じ取って、それを表現しようとしているのです。
こうした遊びのなかで、子どもの音に対する感受性が育ち、集中力が育まれていきます。
◎表現力が身につく
音は耳から入って脳に伝わります。楽器演奏では、受け取った音を今度は手指や腕、全身を使い、楽器を通して表現していくことになります。
楽器を使った遊びは、豊かな表現力を身につけさせることにもつながります。実は、リトミックはそもそも音大生の表現力向上のために考案されたもの。楽譜にとらわれずに音楽を感じる体験は、学生たちの表現力を高める効果があったことから、音楽の専門教育だけでなく、演劇や歌舞伎などのほかの芸術はもちろん、さまざまな世代への「人間教育」のひとつとして広まってきました。
正解を求めるのではなく、感じたままに楽しく音を奏で、体を動かす体験をたっぷりすることで、子どもが持つすばらしい表現力が引き出されていきます。
◎音感やリズム感が育まれる
0〜3歳頃までは「音の敏感期」と言われ、音感やリズム感を身につけるのに適していると考えられています。この時期にたくさんの音楽に触れ、楽器で遊ぶ体験を積むことで、より複雑で高度な楽器演奏にステップアップするときに土台となる音感やリズム感が養われます。
ただ、絶対音感は生まれつきによる部分も大きく、3歳までに音楽教育を始めたからといって必ず身につくとは限らないようです。しかし、基準となる音をひとつ聴けば、そこから正しい音階を奏でることができる「相対音感」は、小学生頃からでも身につきます。
ママ&パパが意識していなくても、赤ちゃんはもうすでにおうちでいろいろな楽器に触れているはずです。たとえば、新生児期から遊べるガラガラだって楽器のひとつ。発展すればマラカスになります。乳児期は、まず音の出るおもちゃを使って、さまざまな音色や音を出す楽しさに触れさせていきましょう。
Point
リトミックでは音楽に合わせて自由に動くことを大事にしていますが、楽器遊びをさせるときにも、子どもの自由な表現を尊重することが大切です。音楽に合わせて、感じたままに手や楽器を振ったり、叩いたり、音を出す遊びのなかで、子どもの発達が促されていきます。楽しい音楽を流しながら、子どもの自由な音遊び、楽器遊びを見守りましょう。
楽器選びは子どもの発達に合わせて

楽器を楽しむためには、子どもの発達に合ったものを与えることが大切です。
0〜1歳代は、マラカスや太鼓のスティックなど、振ったり、握って叩いたりすることで音を出すものがよいでしょう。まだ握力も筋力も弱いので、軽いもの、柄が細くて持ちやすいものを選びましょう。コピー用紙を細く丸め、ビニールテープでぐるぐると補強した手作りスティックもおすすめ。教室でも使っています。
2歳代では、タンバリンなどもう少し大きな打楽器も扱えます。
さらに3歳になると、音階のある音楽も演奏できるように。ただ、まだ指を細やかに動かすのは難しいので、まずは木琴や鉄琴などから始めるのがおすすめ。音階に親しんだら、軽いタッチで音が出るキーボードに触れてみるのもいいでしょう。

ピアノの鍵盤は小さな子どもにはまだ重く、指の骨にも負担がかかると言われています。3歳代はキーボード、4歳頃からピアノへと移行していくとスムーズです。
4歳代では、即興演奏もできるようになります。これまで触れてきた楽器から、子どもが好きなもの、やってみたいものを習ってみるのもいいですね。
上手に演奏することより、楽しむことを大切に

写真提供:ドリームミュージック
楽器遊びをはじめとした音楽教育には、手指の発達を促したり、豊かな情緒を育んだり、集中力や協調性を身につけたりと、さまざまな効果が期待できます。ただ、効果を求めて、親が一生懸命になりすぎてしまうのは考えもの。何よりも大切なのは楽しむことです。子どもの自由な発想や感性を尊重し、見守る姿勢を心がけましょう。
特に、習い事として楽器を練習するようになると、「今日は練習したの?」「楽譜と違うよ!」など、小言を言いたくなることもあるかもしれません。でも、叱られてばかりで音楽を嫌いになってしまっては本末転倒ですね。大きくなってからも楽器を身近に演奏し、楽しみ続けるためには、長く続けることが大事です。
子どもの発達には個人差があります。上達のスピードも子どもによって違います。
「あれ? 楽譜通りじゃないかも」「リズムが間違ってるかも」と気づいても、子どもが集中しているときには注意せずに聴いてあげましょう。
「ママ、聴いてー!」と子どもが声をかけてきたら、ぜひ「がんばったね」「すてきな音だね」とたくさん褒めてあげてくださいね。

井上 幸子/日本こども教育センター代表
リトミック講師歴28年。ニューヨークダルクローズ音楽学校卒、リトミック国際サティフィケイト取得。自身が主催の音楽教室「ドリームミュージック」で現在も講師として年間約200名の生徒を指導。自らが学んだダルクローズメソッドをよりわかりやすく噛み砕き、リトミック教材や英語・知育教材などを開発し、講師の育成にも力を入れる。
また、保育園3園の経営やコンサル会社の代表も務める。著書に『るんるんリトミック』(①巻・②巻)、『生徒が1000人集まる音楽教室の作り方』、『子育てママの「起業」の仕方教えます。』がある。
日本こども教育センター:https://kodomokyouiku.jp/
ドリームミュージック:https://dream-mc.com/