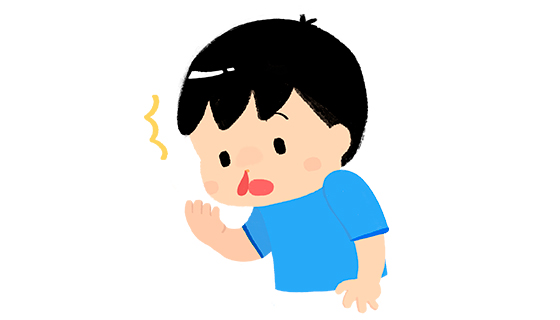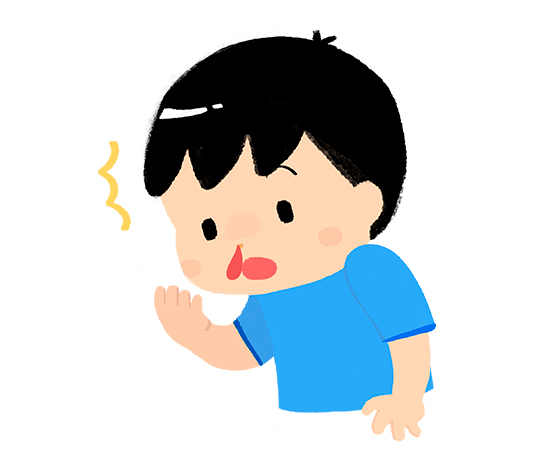インタビューコラム
【前編】パラスポーツは障がいの価値観を180度変えてくれた——クロスカントリースキー・有安諒平選手インタビュー
年々、その注目度を増していくパラスポーツとその競技者であるパラアスリート。多様なハンディキャップを自らの強みとしてとがらせ、一瞬の勝負に挑むその姿に、私たちは感動とたくさんの学びを受け取ります。
今回の主役は、パラローイング(障がい者向けのボート競技)で2021年の東京パラリンピック、クロスカントリースキーで2022年の北京パラリンピックと、夏冬連続でパラリンピックに出場した有安諒平選手。ボートとスキーの二刀流に加えて、生理学を研究する大学院生、そして2022年に生まれた娘さんのパパという顔を持つスーパーマンです。
【前編】では、これまでの人生とパラスポーツとの出会いについて、お話をうかがいました。

Profile
有安 諒平(ありやす・りょうへい)
1987年、アメリカ・カルフォニア州で生まれ、5歳で日本に帰国。15歳のときに黄斑ジストロフィーを発症し、視覚障がい者となる。大学時代にパラ柔道に出会い、29歳でパラローイング(ボート)、32歳でパラクロスカントリースキーをスタート。2021年の東京パラリンピックにはローイングで、2022年の北京パラリンピックにはクロスカントリースキーで出場。2022年1月に長女が誕生。杏林大学医学研究科(博士課程)、東急イーライフデザイン所属。
やりたいことを自由にやれていた幼少期
——まずは幼少期の頃から振り返らせてください。幼少期はどんなお子さんでしたか?
マイペースで、やりたくないことはやらないタイプだったようです。宿題をしないから「指定した範囲を覚えてきなさい」みたいなテストで全然点数が取れなかったし、小学校高学年の頃、受験塾の夏期講習の途中で窓から逃げ出したことがありました。親はこれで「諒平は勉強が好きじゃないんだな」と認識したようで、以降はかなり自由に育ててもらいました(笑)。
——「勉強しなさい!」と怒られるようなことはあまりなかったんですね。
「やっておきなさいよ」くらいは言われましたけれどね。学校の先生にはすごく怒られた記憶がありますけど、親はそうでもなかったと思います。やってみたいと思ったことを「ダメ」と言われたこともなかったですし、本当に自由にやらせてもらっていましたね。物心ついてから友達が「親がうるさい」みたいなことを話すのを聞くたびに、「そういうことを言われたことがないな」って思っていました。今、僕には2歳になる娘がいるのですが、自分が親になって初めてその偉大さを思い知りましたし、ちょっとリスペクトも出てきました。
——スポーツはされていましたか?
スイミング、テニス、サッカーといろんなことをさせてもらいましたが、どれも全然定着していなかったです。そもそもスポーツ自体もそんなに好きじゃなかったですね。ただ体を動かすのは大好きで、虫捕りをしたり、雑木林で落ち葉や枯れ木を集めてサツマイモやリンゴを焼いたり、友達と外でずっと遊んでいました。
障がい者手帳をしまい込んだ高校時代
——視力に異変が出たのは12歳頃とうかがっています。
小学校高学年の頃、床に散らばった輪ゴムを片付けていたときに、父から「全部片付けなさい」「取ったよ」「残ってるじゃないか」「ないよ」というやりとりをしたことがありました。これが目が悪くなり始めた最初の記憶です。その後だんだん黒板が見づらくなって、近視用のメガネをかけるようになったけれど調整がうまくいかず、大きい病院に行っていろいろな検査をして「黄斑ジストロフィー」という病気だと判明しました。
——そこから治療が始まったのですか?
成長とともに視力や視野の異常が進行して、大人になるとそれが止まったりゆるやかになるという病気で、特に治療法がないので、対症療法的にメガネで視力矯正をしたくらいです。37歳の今はかなり進行がゆるやかになっていますが、街を歩いている人の性別や姿形はほとんどわからず、夜間に外出するときには白杖を持ちます。
——診断を受けた際には、病状が進行していくことも説明されましたか?
あったと思うんですけど、あまり覚えていないです。病名がはっきりして、障がい者手帳が交付されるという説明を受けたのが中学の終わり頃でしたが、まさか自分が障がい者だとは思っていなかったし、障がいを持っている友達もいなかったですし、高校1年生で手帳が交付されてからもしばらくは机の中にしまい込んだままでした。
——ご両親と病気について何かお話をされましたか?
親も当時はショックを受けて、どうにかならないものかと右往左往していたようですけど、僕にはあまりネガティブなところを見せなかった記憶があります。僕自身が病気のことに触れられたくなかったから、それを察してあえてほったらかしにしてくれたという感じですね。
——学生時代はメガネをかけていれば日常生活は問題なかったのですか?
当初は、メガネをかけて座席を先生の教卓の目の前に持っていってもらえばなんとかなっていましたが、中学2年生以降はそれでも見えなかったので、一番前の席に座りながら望遠鏡を使って黒板を見ていました。教科書は1ページずつA3版に拡大コピーして、ルーペを使って読んでいました。
あの頃は、先生やクラスメイトに変にケアされるのが嫌で、なるべく視力のことがバレないようにと必死でしたね。勉強を一生懸命やろうとすればするほど、目が悪いことを伝えなきゃいけないので「勉強してないからできません」っていう雰囲気を出していましたし、体育の授業もフェンスの横で友達とくっちゃべってサボっていました。障がいが表に出てしまいそうなことからは自分から身を引いていたんです。
——そのような状況から、どのようなプロセスを踏んで障がいを受け入れられたのでしょうか。
最初のきっかけは、障がい者手帳でした。暇なときに開いてみたら、電車賃が半額になったり、映画が1000円で観られたり、いろいろサービスみたいなものが受けられることを知って、「お得じゃん」と思って(笑)。その頃には「目が悪い人」としての生活にも慣れてきて、「目が悪い」というステータスを徐々に自分の一部として受け入れられるようになっていました。
とはいえ、目が悪いとできないことはたくさんあります。たとえば運転免許は取れませんし、「あの子がかわいい」みたいな話題にもついていけない。そういうときには改めてショックを受けて、受容と拒絶を行ったり来たりしていたんですが、パラスポーツに出会ったことで本質的に障がいを受け入れられるようになりました。
——大学時代、ご友人の紹介でパラ柔道を始められたときですね。
はい。それまで僕にとってのスポーツは、やればやるほど「できない」「目が悪い」ということを直視させられる嫌なもの…さらに言うと足かせだったんですけど、パラスポーツと触れ合って、その先にパラリンピックという可能性があると知って、「目が悪くてラッキーだったな」「目が悪いほうがいいじゃん」って初めて思ったんですね。障がいの価値観を本当に180度ひっくり返してくれたっていうことでは、パラスポーツとの出会いは本当に大きなものだったと思います。
——以前、別の競技でメダルを獲られたパラリンピアンを取材させていただいたことがあるのですが、その方も「障がいがあったからパラリンピックに出られたし、ラッキーだった」とおっしゃっていました。
パラアスリートって自分の障がいをプラスに捉えて、メリットとして、そこに全力投球することで活躍している人たちだと思うんです。そういう意味で、本質的に障がいを昇華している存在といえるんじゃないかなと思いますね。
トレーニングの一貫で始めたクロスカントリースキーで冬季パラをめざす

——柔道を通して本格的にスポーツに打ち込んでみていかがでしたか?
楽しかったです。ただ柔道が向いてたのかはちょっとわからないですね。闘争心が高いタイプではないので、ガシガシ向かってくる相手がちょっと怖くて(笑)。大学院に進んでからも細々と競技を続けていた頃に、東京パラリンピックの開催が決まりました。自国開催だし、人生は1回だし、自分もそこにチャレンジしたいという気持ちになったときに、別の競技への転向を模索し始めたんです。そして、東京都の選手発掘プログラムに参加してボートに出会いました。
——そこからさらにクロスカントリースキーを始められたきっかけは何だったんですか?
「オールを漕ぐ」という単一の動作を突き詰める特性上、ボートはオーバートレーニングになりやすい競技なので、自転車を漕いだり、走ったり、ボート以外のトレーニングに多く取り組みます。その中で何をしようかなと考えていたときに、オリンピックの日本代表チームが冬にクロスカントリースキーをやると知りました。
さらに調べてみると、夏はボート、冬はクロスカントリースキーという競技生活を送っている人は世界的にけっこういると知ったので、自分もやってみようと思いました。
知人を介して、視覚障がい者のガイドスキーをやっている藤田佑平くんを紹介してもらい、トレーニングをしていくうちに「どうせだったらパラリンピックを狙っていきましょうよ」と背中を押され、2026年のミラノ・コルティナ冬季パラを狙うことを決めました。
僕としても、ボートの強化合宿に参加させてもらえるようになって、パラリンピックに出る以上のことをやってみたいという欲が出てきていたので、それだったら夏季と冬季、両方のパラリンピックに出るというチャレンジをしてみようと思うようになりました。
【後編】 では、クロスカントリースキーのことや2022年に生まれた娘さんの育児について、お話をうかがいます。