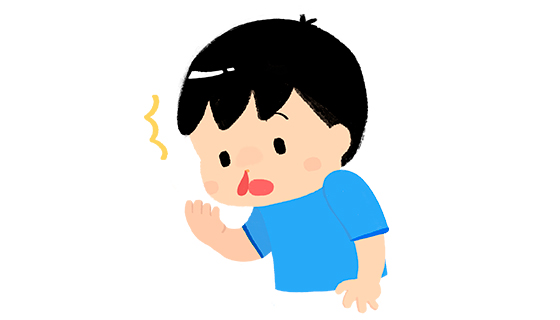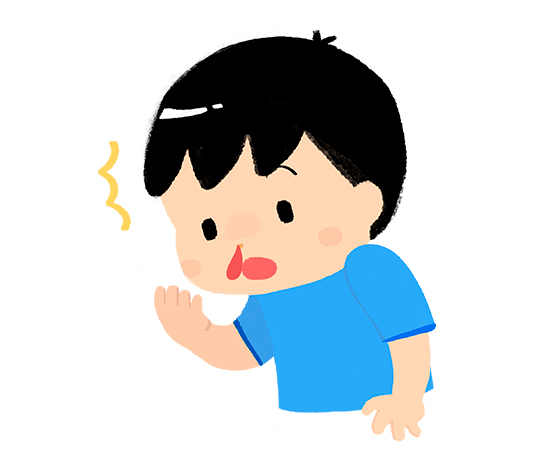mama知っ得!情報
室内で「伝承あそび:かかしのケンパ」をやってみよう!
これからやってくる梅雨の時期は、どうしても“室内あそび”がメインになりがち。
そこで今回は、名城大学の香村恵介先生に、室内でも楽しく&しっかり体を動かせる「伝承遊び:かかしのケンパ」を教えていただきました。
家族みんなでチャレンジして、心と体をほぐしましょう!
幼児教育の場で注目されている「伝承あそび」とは?
「伝承あそび」という言葉を聞いたことはありますか?
伝承あそびは、古くから日本で親しまれてきた、 “子どものあそび” のこと。「ゴム跳び」や「おはじき」「花いちもんめ」「かごめかごめ」など、いろいろな種類がありますが、今回、香村先生が教えてくれたのは「かかしのケンパ」です。
「『かかしのケンパ』は、かかしに見立てて描かれたマスを、片足ジャンプ、両足ジャンプしながら進むあそびです。
本来外で行うあそびですが、室内でもやっても大丈夫。
片足でジャンプしたり、片足で物を拾ったりすることでバランス感覚が身につきますし、マスをねらって物を投げることで用具を操作する能力も養えます」
実は、「かかしのケンパ」をはじめとする伝承あそびは、近年、幼児教育の場であらためて注目されているのだとか。その理由について、香村先生は次のように話してくれました。
「伝承あそびは、特別な道具を必要としないので、誰でも、どこでも手軽にできます。また、ルールがシンプルなため、子どもの年齢や興味、運動能力に合わせてあそび方をアレンジできるのも魅力です。さらに、子どもたちが話し合ってルールを工夫する余地もあり、自主性や協調性、創造性を伸ばすきっかけにもなります。こうした点が見直されて、あらためて伝承あそびが注目されているのです」
ではさっそく、あそび方をご紹介しましょう!
「かかしのケンパ」に挑戦してみよう!
◆基本編
片足で「ケンケン」して、両足で「パ」と着地する「ケンパ」をしながら、かかしに見立てたマスを進んでいきます。ジャンプしたときにすべらないよう、靴下を脱いでからあそんでくださいね。
【家でもできる子どもの運動】かかしのケンパ(全年齢向け)
《準備するもの》
・マスキングテープや養生テープなど、はがせるタイプのテープ
《基本のやり方》
① 下のイラストを参考にして、マスキングテープなどで床に8つのマスを描きます。1つのマスの大きさは、子どもの足より少し大きい程度が目安。△の部分が笠をかぶったかかしの頭、□のマスが3つ横に並んだ部分がかかしの腕(両腕を広げているイメージ)です。

※マス目の中の番号は、実際には書かなくてもかまいません。
② かかしの足のほうから、「ケンケン、パ、パ」のリズムでケンパをしていきます。
1 と 2 のマスを片足で「ケンケン」して進んだら、3 と 4 のマスに両足で着地して「パ」。
そのまま横にジャンプしながら、4 と 5 のマスに両足で着地して「パ」となります。
「ケンケン、パ、パ」と声を出しながら、かけ声に合わせて移動してくださいね。
③ 6 のマスは片足で「ケン」、7 と 8 のマスは両足で着地して「パ」でゴールです。
④ 1~8 のマスまでスムーズにケンパができるようになったら、今度はかかしの頭のほうからスタート!
基本的な跳び方は、②、③と同じです。
7 と 8 のマスは両足で「パ」、6 のマスは片足で「ケン」、5、4、3 のマスは両足で横に移動して「パ、パ」、2 と 1 のマスで「ケン、ケン」となります。
◆応用編
【基本編】ができるようになったら、【応用編】に挑戦してみましょう。
応用編では「ペットボトルなどのキャップをマスの中に入れる」「マスをよけてジャンプする」「マスの中のキャップを拾う」
という動作が追加されます。
※【応用編】は基本的に 2人以上で行ってください。
《準備するもの》
・マスキングテープや養生テープなど、はがせるタイプのテープ
・ペットボトルなどのキャップ(いらない紙を丸めたものなどでもOK)
《やり方》
① 【基本編】と同様、マスキングテープなどで床に 8つのマスを描いておきます。
次に、1のマスから少し離れた場所にテープを貼って、スタート位置を設定。スタート位置から、1のマスに向かってキャップを投げましょう。
1のマスに入らなかったら、次の人と交代です。

② キャップがマスの中に入ったら、【基本編】と同様にケンパをスタートします。
ただし、1のマスから8のマスに向かう「行き」のときは、キャップが入っている1のマスを踏まないように、よけるのがポイント。
1のマスの手前に立ったら、1のマスを跳び越して2のマスに「ケン」で着地します。あとは、普通にケンパで進みます。
③ 7、8のマスに「パ」で着地したら、両足でジャンプして体の向きを180度変えましょう。
続いて、1のマスに向かってケンパで進みます。
ただし、この「帰り」のときは、1のマスに入っているキャップを拾うのがルール。2のマスに「ケン」で着地したら、片足立ちのまま、1のマスのキャップを拾いましょう。
キャップを拾ったら、1のマスに「ケン」で着地して終了です。

④ ③をクリアできたら、次は、2のマスを狙ってキャップを投げます。
その後の手順は①~③と同じです。「行き」はキャップのある2のマスを跳び越し、「帰り」はキャップを拾いましょう。
⑤ これを8マス目まで続けます。
香村先生からのアドバイス
【基本編】をやるときは、まず、ママやパパが実際にやってみせてあげましょう。
子どもが興味を示したら、「ママ(パパ)の後ろについて、ママ(パパ)と同じようにやってみてね」といって、コツを覚えるまで一緒にやってみてください。
最初のうちは、ケンパがうまくできないかもしれませんが、そんなときはできないことを指摘するのではなく、「ママのまねが上手にできたね」という具合に、できたことを見つけてほめてあげてくださいね。
【応用編】をクリアできたら、「きき足ではないほうでケンパをする」「キャップをきき手ではないほうで投げる」など、いろいろとアレンジしてみてください。
かかしの笠の上に 〇 を描いたり、足の部分に □ を付け足したりして、マスを増やすのもおすすめです!
みなさん上手にできましたか? 何度もジャンプするので、実際にやってみると意外とハードなのがわかるはず。運動不足が気になるママやパパにも最適ですよ!
なお、室内でうんどう遊びを行う際は、十分なスペースを確保して、ケガのないように注意してくださいね。
※動画では、このほかにもさまざまな「かかしのケンパ」のやり方を紹介しているので、そちらにもぜひ挑戦してみてください。

香村恵介/名城大学農学部 教養教育部門体育科学研究室 准教授
幼少期の子どもたちが心身ともに健康で運動好きになることを目指し、子どもの体力・運動能力や身体活動量に関連した研究に取り組む。
『親子でたのしむ 日めくり うんどうあそびカレンダー』(子育て世代応援プロジェクト実行委員会)を監修。
「家でもできる子どもの運動」をYouTubeにて公開中。
●家でもできる子どもの運動
https://www.youtube.com/channel/UC4PJNKQW-CvD3SV0C406Qog
制作協力:八藤直樹(学校法人京都城南学園 向島幼稚園 体育指導主任)、子育て世代応援プロジェクト実行委員会