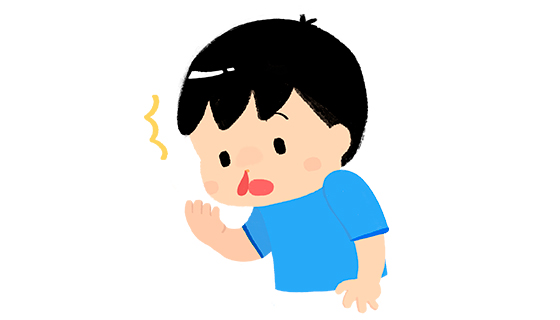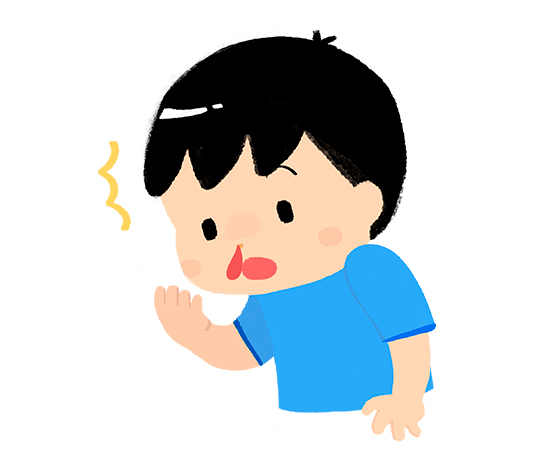mama知っ得!情報
いま注目の教育法、「モンテッソーリ教育」とは?【前編】

みなさんは、「モンテッソーリ教育」についてご存じですか? モンテッソーリ教育とは、20世紀初頭にイタリアで考案された教育法のことです。将棋界最多の公式戦29連勝を達成した、プロ棋士の藤井聡太さんも幼稚園でモンテッソーリ教育を受けており、近年、日本でもその注目度が高まっています。
そこで今回は、モンテッソーリ教育の基本的な考え方や特徴、家庭で実践するためのポイントなどについて、日本モンテッソーリ教育綜合研究所附属「子どもの家」副園長の櫻井美砂先生に伺いました。
世界中で支持されているモンテッソーリ教育
モンテッソーリ教育は、ローマ大学最初の女性医学博士マリア・モンテッソーリによって考案された教育法です。マリア博士は、もともと障がい児の治療教育に携わっていましたが、その分野で大きな成果をあげたことで、貧困層向けのアパートに設けられた保育施設の監督・指導を任されることになりました。博士は、そこで子どもたちと触れあいながら、障がい児にも用いていた教育法を実践。独自の教育体系や教具を開発するなどして、モンテッソーリ教育を完成させていきます。
その後、モンテッソーリ教育は、時代や文化の違いを超えて世界各国で支持されることになりますが、モンテッソーリ教育と一般的な教育法とでは、何が違うのでしょう? まずは、櫻井先生にモンテッソーリ教育の特徴について聞いてみました。
「モンテッソーリ教育では、『子どもは皆、自己教育力を備えている』という前提に立って教育が行われます。自己教育力というのは、『自分を伸ばす力』のことで、歩くことを教えなくても歩こうとしたり、積極的に環境に関わりながらいろいろなことを吸収していったりする姿は、まさにそのあらわれ。子どもは自分が成長するには何が必要なのかを知っていて、それを実践する力があるのです。ですから、子どもが何かをやりたがったら、それはその子どもにとって成長するために必要な課題であり、存分に取り組ませることが大切だと私たちは考えています」
事実、モンテッソーリ教育の実践施設である「子どもの家※」では、「今日はみんなでお絵描きしましょう」「絵本を読みましょう」と一斉指導を行うことはあまりありません。「今日何をするか?」は、子どもたち自身が考えて選ぶのだそうです。
※マリア博士が監督・指導を任されていた保育施設が「子どもの家」という名称だったことから、モンテッソーリ教育を実施する施設は「子どもの家」と呼ばれています。
子どもたちの「やりたい」という思いを尊重することが大事
モンテッソーリ教育では、子どもが自らやりたいと思う活動、つまり自己教育力に促されて取り組む活動を「おしごと」と呼びます。おしごとのために必要な教材を「教具」と呼びます。モンテッソーリ教育におけるおしごとは、下の表に示した5つの分野(2歳半~6歳までの一例)。「子どもの家」に当園した子どもたちは、教具や教具を使うエリアを自分で決めて、おしごとに取り組みます。
| 日常生活の練習 | 歩く、包丁で切る、コップに水をそそぐ、ボタンをかける、室内を掃く、アイロンをかけるなど、実生活と密接に関連する多くのおしごとが用意されています。包丁やほうき、アイロンといった「用具※」は、子どもが扱いやすいサイズや形状になっています。 ※日常生活の練習に用いられるものは、「用具」と呼ばれています。 |
| 感覚教育 | さまざまな教具を使ったおしごとを通じて、わずかな大きさ、形の違いを見わけたり、音を聞きわけたり、微妙な匂いや味、色を区別したりといった感覚を育みます。また、感覚を洗練しながら、知性の覚醒も目指します。 |
| 言語教育 | 絵や文字が書かれた教具を使い、おしごとをします。子どものことばの発達を促します。 |
| 算数教育 | 数量を具体的にあらわしたビーズや棒などを使って、数の概念や四則計算に関するおしごとをします。具体的な数量体験を十分に積み重ねながら、数という抽象の理解へと導きます。 |
| 文化教育 | ミニサイズの国旗や世界地図パズル、時計の模型などの教具を使います。子どもたちはおしごとを通じて、歴史、地理、地学、動・植物など幅広い分野に触れます。 |

包丁を使って切る(日常生活の練習)

色板(感覚教育)
さて、ここまでを読んで「それだと、子どもたちは毎日自分の好きなおしごとばかり選んでしまうのでは?」「できることがかたよってしまうのでは?」と思われた方もいるかもしれません。この疑問に対して、櫻井先生は次のように答えてくれました。
「子どもが自ら『やりたい』と思って選んだおしごとは、その子どもの発達に必要な課題です。ある特定のおしごとばかり選ぶのも、同じ行為を何度もくり返すのも、その子にとってそれだけ重要だからであって、決して悪いことではありません。本人が納得できるまで習熟できたら、自然とほかのおしごとに興味を示すようになります」
また、櫻井先生は「大人には同じ行為のくり返しに見えても、子どもにとってそうとは限らない」とも指摘します。
「大人は、『同じ行為をくり返すのは時間の無駄だ』と考えがちです。でも子どもは、『今回は、〇〇のところがさっきより上手にできた』『今度はもっと△△が早くできるようになった』という具合に、違う課題を持って取り組んでいたりするもの。『子どもにはいろいろな経験をさせたい』というママやパパの気持ちもわかりますが、それはあくまでも大人の価値観です。まずは、子どもの意志を尊重してあげましょう」
予測不可能な世界を、幸せに生きるための力が身につく
モンテッソーリ教育が日本にはじめて紹介されたのは1912年のこと。当時は、早期教育として話題になったそうですが、世の中に定着するには至りませんでした。では、それから100年以上経った現在、あらためて注目が集まっているのはどういう理由からでしょう。櫻井先生は次のように推測します。
「いま、世界はどんどん複雑化し、かつてないスピードで変化しています。これから世界がどのように変わっていくのか、誰も予測できません。そうしたなか、従来の“知識詰め込み型”の教育に不安を覚え、『どんな時代・世界であっても、自分の持っている能力を存分に発揮して、幸せに生きる力を子どもたちに身に付けさせたい』と願う人は確実に増えています。そのニーズにモンテッソーリ教育の理念がマッチしたことで、このように注目されているのではないでしょうか」
ちなみに、Google、Amazon、Facebook、Wikipediaといった世界的な企業の創業者たちも、モンテッソーリ教育を受けているといいます。また、イギリスのウィリアム王子とキャサリン妃が、長男ジョージ王子のために選んだ幼稚園も、モンテッソーリ教育を掲げる幼稚園でした。そして、先に紹介した将棋界の若き天才・藤井聡太さんも、モンテッソーリ教育の幼稚園に通っていた一人です。このように、時代をけん引するような人物たちがモンテッソーリ教育を受けていたという事実も、近年、モンテッソーリ教育が注目を集めている理由といえるでしょう。
モンテッソーリ教育の考え方や特徴について、おわかりいただけましたか?
【後編】 では、モンテッソーリ教育を家庭で実践する方法についてご紹介しますので、そちらもぜひお楽しみください!

櫻井美砂
日本モンテッソーリ教育綜合研究所附属「子どもの家」副園長
日本モンテッソーリ教育綜合研究所主任研究員
一般の幼稚園にて10年間勤務した後、子どもの家」の副園長として、日々、子どもたちの成長をサポートしている。
●日本モンテッソーリ教育綜合研究所
https://sainou.or.jp/montessori/