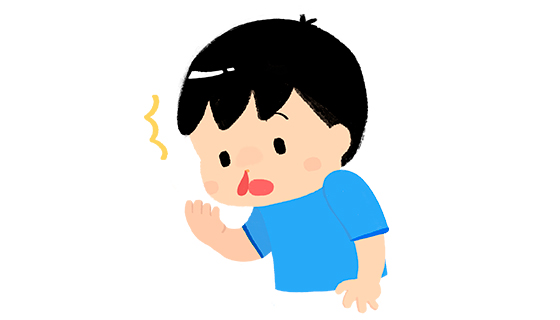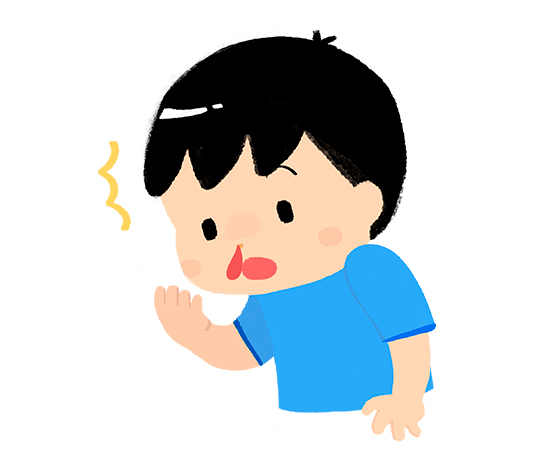mama知っ得!情報
いま注目の教育法、「モンテッソーリ教育」とは?【後編】

【前編】では、モンテッソーリ教育に関する基礎知識をお伝えしましたが、読んでいるうちに「モンテッソーリ教育を家庭でも実践してみたい!」と思ったママやパパも多いのでは? そこで【後編】では、日本モンテッソーリ教育綜合研究所附属「子どもの家」副園長の櫻井美砂先生に、モンテッソーリ教育を家庭で実践するためのポイントについて教えてもらいました。
家庭でモンテッソーリ教育を実践するポイント
では、さっそくモンテッソーリ教育を家庭で実践するためのポイントについてご紹介しましょう。
ポイント① 子どもをしっかりと観察して、理解しよう
おもちゃを使って遊ぶにせよ、何かしらのお手伝いをしてもらうにせよ、まずは子どもが何に興味を持ち、どんな活動をしたがっているのかをしっかり観察しましょう。このとき、「これができるようになってほしい」「この年齢なら、これくらいはできるべきだ」という大人の都合や価値観を持ち込まないことが大切です。
<櫻井先生からのアドバイス>
すべての子どもは、自分自身を育てる力、すなわち「自己教育力」を生まれながら持っています。そして、子どもたちはその自己教育力に導かれて、自分の発達に必要な環境に関わっていきます。子どもたちが何に興味を持ち、何をしたがっているのかを観察することは、子どもの特性や発達段階を理解するきっかけにもなりますよ。
ポイント② 「まだ小さいから無理」と決めつけない
私たち大人は、子どもが何かしようとしても、「まだ小さいから無理」「まだこの子にはできない」と決めつけてしまいがちです。「でも実際には、子どもが使いやすい道具や環境を用意してあげることで、できることも多いんですよ」と櫻井先生は話します。たとえば、子どもが洗濯に興味を示したとしましょう。子どもの身長では、物干しざおに洗濯ものをかけるのは無理。けれど、子どもの手が届く高さにハンガーなどをかけてあげれば 子どもでも「干す」という行為は実践できます。
<櫻井先生からのアドバイス>
自分自身を育てるのは、子どもの役目です。そして、子どもが自分自身を育てられるような環境を整備・用意してあげることが、私たち大人の役目です。子どもが存分に自分を育てられる環境を整えてあげましょう。
ポイント③ やり方は言葉で教えるよりも、実際にやってみせる
「環境を整備・用意する」以外にも、大人にはもう一つ、大切な役目があります。それが、「やってみせる」ことです。モンテッソーリ教育ではこれを「提示」と呼び、子どもの成長発達を手助けする要素として重視されています。
<櫻井先生からのアドバイス>
環境が整っていても、やり方がわからなければ、子どもは自己教育力を発揮できません。乳幼児期の子どもは、ママやパパのやっていることをまねしたがるもの。ですから、子どもが何かの活動に興味を持ったら、ママやパパは、最初にやり方を見せてあげましょう。モデルになったつもりで、一つひとつの動きをゆっくり見せてあげるのがコツ。口で説明するよりも伝わります。
ポイント④ 「声かけ」のタイミングに注意
子どもが何かをする際、苦戦していたり、やり方が間違っていたりすると、つい声をかけたくなってしまいますよね。けれど、子どもにすぐに正解を教える行為は、子どもが自分で考える機会を奪ってしまうことになりかねません。うまくできなかったり、間違ったやり方をしたりしても、「それでいいのかな?」「それで合っているのかな?」といわずに、ちょっと待ってみましょう。何度かくり返すうちに、上手にできるようになるかもしれませんよ。
なお、ほめるときも、声かけのタイミングには注意が必要。櫻井先生によると、ほめることで、子どもの集中を妨げてしまう場合もあるのだそうです。子どもは集中がいったん途切れてしまうと、再び集中するのが難しいもの。集中しているようなら、やり終えるまで待ってから、「よかったね!」「最後までがんばったね!」とがんばりを認めてあげましょう。
<櫻井先生からのアドバイス>
「自分でできた!」という達成感を味わうことは、子どもたちの自己肯定感を育むことにつながります。自己肯定感があれば、失敗をおそれず新しいことにも意欲的にチャレンジできるようになり、たとえ失敗しても、失敗した自分を受け入れられるようになるはず。声がけするときは、しっかり観察しタイミングを見計らって行いましょう。もし、うまくできず、あきらめて投げ出しそうになったら、「やってみるね」と言って、やり方を提示してあげるとよいでしょう。
ポイント⑤ どうすればいいか迷ったら、子どもを見る
ポイント④で、「見守る」ことの大切さについて説明しましたが、「見守る」と「放任する」は違うのだと櫻井先生は言います。「たとえば、子どもが水をこぼしたとき、『この子はこのあとどうするのか』とただ見守っていても仕方ありません。対処法を知らなければ、子どもは驚いたり、騒いだりして終わりです。そんなときは、『水がこぼれたね。こぼれたら、この雑巾でふこうね』という具合に、やり方を提示してあげましょう。そして、興味を示したら、子ども自身にやらせてみてください」。
その際、雑巾が普通のサイズだと子どもの手に余ってうまくふけない可能性もあるので、子ども用の小さめの雑巾を用意してあげましょう。子どもを管理しすぎず、放任せず、適切に見守る。この「さじ加減」は、ぜひ身につけたいところです。
<櫻井先生からのアドバイス>
どこまで見守って、どのタイミングで手助けするべきかは、子どもの性質や発達段階によっても違ってきます。見守るべきか、サポートするべきかの判断に迷ったら、とにかく子どもをしっかり観察してみましょう。そうして試行錯誤しているうちに、お子さんに合ったさじ加減がわかってくると思いますよ。また、大人の側が自分自身を俯瞰して、自分が管理しすぎていないか、あるいは放任していないかを適宜確認することも大事です。
モンテッソーリ教育を実践するためのポイントについて、最後に、櫻井先生のこんなアドバイスもご紹介しておきます。
「テレワークやリモート授業が増え、お子さんといる時間が増えたママやパパも多いはず。
この機会に、子どもをじっくり観察して、『子どもがやりたいこと』ができるように、環境を整えてみてください。
忙しくてなかなか時間がとれないときは、お皿を運ぶ、お花の水を入れかえる、グラスに水を注ぐなど、子どもが興味を示した行為を、ゆっくりとやってみせるだけでもいいと思います。
それだけで、子どもはいきいきと、主体的に行動するようになりますよ」
一緒に過ごす時間が増えているいまだからこそ、子どもたちをしっかりと見つめ直し、しっかりと寄り添いたいものですね。みなさんも、実践できることから少しずつはじめてみてください!

櫻井美砂
日本モンテッソーリ教育綜合研究所附属「子どもの家」副園長
日本モンテッソーリ教育綜合研究所主任研究員
一般の幼稚園にて10年間勤務した後、子どもの家」の副園長として、日々、子どもたちの成長をサポートしている。
●日本モンテッソーリ教育綜合研究所
https://sainou.or.jp/montessori/