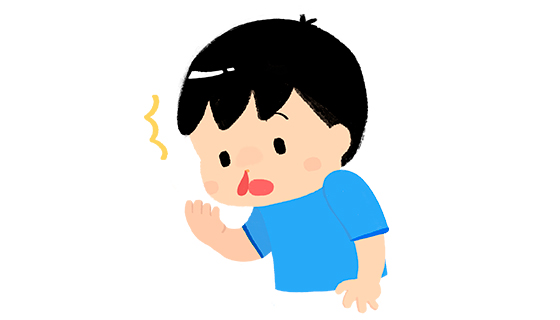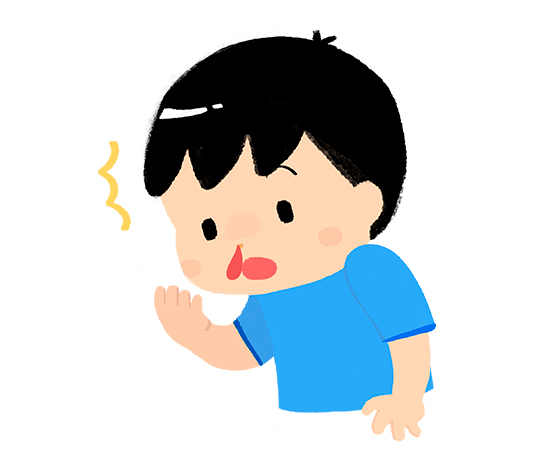mama知っ得!情報
他の子と比べると落ち着きがないことが多いようで心配しています

1歳が過ぎて体の発達がすすみ運動能力が向上した子どもは、走ったり跳んだり、いつまでも動きまわっていることがあります。2歳過ぎの好奇心旺盛な子どもは、目にするものに次々に関心が移り、せわしなく、ひとつの遊びに集中しない様子がみられることもあります。遊びに夢中になっている子どもというのは、周りからの声が届かないため、その場の状況にあわせて行動することが難しいものです。子どもの生活が家庭から集団の場に広がることで、まわりの子どもと比べる機会も増えますから、落ち着きのないわが子の様子を目にして驚き、発達上の問題ではないかと心配になることもあるでしょう。
子育て中の心配ごとを相談できる人や窓口があれば、育児への安心感や自信につながるものです。地域の保健センターには保健師が在席しているので、まずは気軽に利用してみるとよいでしょう。3歳6か月健診は子どもの発達の標準に対する偏りについて注意が払われているので、落ち着きのなさが心配であれば、具体的に相談するよい機会となります。健診時の指摘は、発達の遅れに対する診断ではなく、子どもの困りごとへの早期の支援と療育のきっかけになるものです。保護者の方にとっては、子どもへの関わり方を専門家と探るチャンスと考えてもよいかもしれません。
保育園や幼稚園などの通園先で、落ち着きのなさについての指摘を受けた場合には、いつ、どのような時に子どもの落ち着きのなさなどの問題が起きるのか…まずは、通園先の先生と相談しながら、集団のなかでの子どもの情報を集め、困っている子どもの状況を確認します。状況を確認することで、具体的な子どもへの関わり方を見つけてみましょう。子どもの落ち着きのなさに改善がみられないのであれば、発達の偏りを確認する観点から、かかりつけの小児科に相談することをお勧めします。
ご家庭では、たとえば動きまわって落ち着かない子どもに対しては、身体をめいっぱい動かす時間をつくるだけではなく、静かな環境と集中する時間を生活のなかに取り入れることで、子どもの心の安定につなげることができます。夢中になっている子どもに何か伝えたい時には、子どもと視線をあわせ、短い言葉で、簡潔に話すことも有効な手段となります。
発達途上の幼児期というのは、落ち着きのなさが子どもの「性格」なのか、「年齢」を理由とした発達の未熟さのためなのか、「個人差」とも、「発達の遅れ」とも判断がつかないこともあります。そのような悩ましい時にこそ、相談窓口と頼れる人に出会えれば、日々の育児がより楽しくなるのではないでしょうか。
東京海上日動メディカルサービス 発行
http://www.tokio-mednet.co.jp/