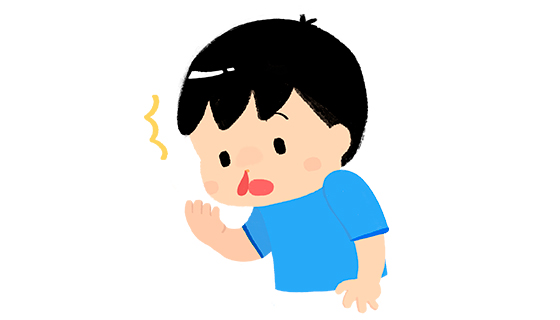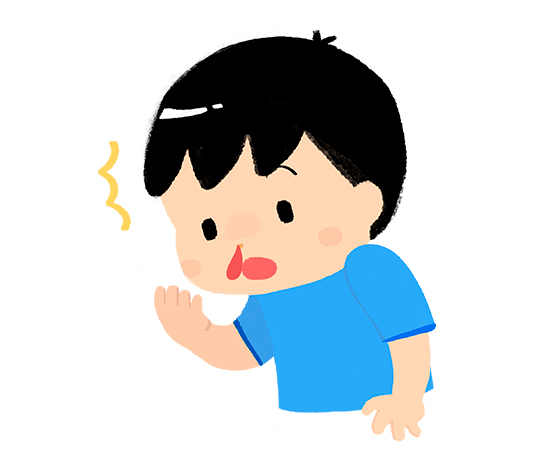mama知っ得!情報
キャンプから帰宅したらマダニが付いているのに気づきました。対処方法は?

マダニとは?
マダニは山林や草むら、ヤブなど、特に野生動物がいるような自然環境が豊かな場所に多く生息します。市街地の近くでも、畑やあぜ道などに生息していることがあります。地上1m位の植物の葉陰で待ち伏せ、近づいた動物や人に取り付いて、長時間(数日~10日間以上)吸血します。
マダニの成虫は体長が3~8mmで肉眼でも見えます。吸血し満腹状態になると更に10~20mm程度の大きさになります。基本的に春から秋にかけての暖かい季節に活発に活動しますが、温暖な地域では冬でも活動しています。
マダニに咬まれないようにするには
1. マダニが生息していそうなところに入るときに肌を露出しないことが大切です。長袖や長ズボン、足を完全に覆う靴、帽子、手袋を着用し、首にタオルを巻く等、露出を少なくしましょう。
2. マダニにも効果があるとされるDEET(ディート)やイカリジン※という成分を含む虫除け剤もあります。使用上の注意などをよく読み、用法容量を守って、利用するのもよいでしょう。
3. マダニが生息していそうなところから帰ったら、衣類や体にマダニが付いていないかをよく確認し、シャワーや入浴で洗い流しましょう。また着用していた衣類は放置せず、すぐに洗濯しましょう。
※DEET・イカジリン:多くの忌避剤(虫除け剤)の中でも特に効果が示されている有効成分のことです。マダニ以外に蚊やアブ、ブヨなどの虫除けとしても使用できます。現在、成分濃度等が調整された様々な商品が出ていますので、使用者の年齢や使用環境に合わせて、よく説明書きを確認して選択してください。
咬まれていることに気づいたら
マダニに咬まれていることに気づいたら、無理に取ろうとせず、皮膚科や外科を受診して除去・洗浄をしてもらいましょう。自分で取ろうとすると、虫体の一部が残ってしまったり、傷の炎症を起こすことがあります。 また、マダニをそのまま付けた状態で受診した方が、医師がマダニかどうかの判断がしやすくなります。もし自分で取ってしまった場合でも、病院で傷口の診察を受けるのがよいでしょう。
ダニ媒介感染症について
日本国内でマダニに咬まれて感染するリスクのある病気としては、日本紅斑熱やライム病、ダニ媒介性脳炎、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)などがあります。ただし、全てのマダニが病原体を持っているのではなく、咬まれたからといって必ず感染するわけではありません。
これらの病気にもし感染したとしても、症状が出ていないうちは検査することはできません。潜伏期間があるため、咬まれてから3週間程度は発熱、倦怠感、関節痛、発疹、腹部症状(腹痛、嘔吐、下痢、食欲不振)などの症状が出ないか経過観察をしましょう。もし症状が出たら内科を受診して、必ずマダニに咬まれたことを申告し、いつ・どこで・体のどこを咬まれたのかを医師へ伝えてください。治療には、どの病気かによって特効薬となる抗生剤がある場合もあれば、特効薬はなく対症療法のみの場合もあります。早めの診断・治療開始のために、症状が出たら速やかに受診をしましょう。
東京海上日動メディカルサービス 発行
http://www.tokio-mednet.co.jp/