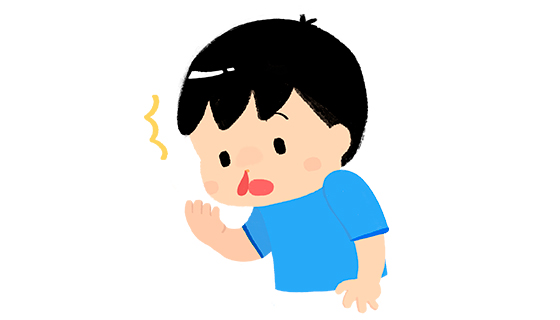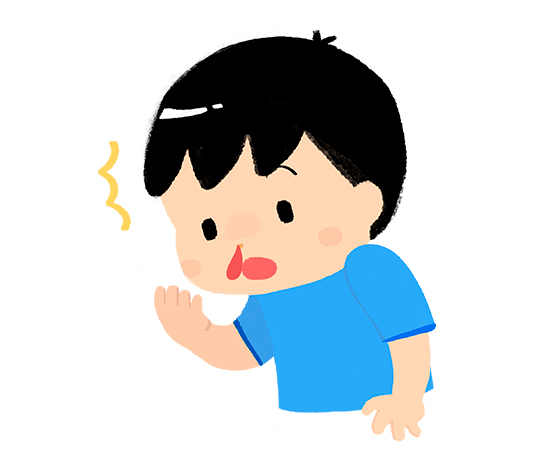mama知っ得!情報
歯ならびに影響するものは? いい歯ならびの育て方

お口の健康が全身にも影響を与えることは、よく知られるようになってきました。むし歯や歯周病のない健やかな口腔環境は、子どもにとってももちろん大事! 同様に歯ならびも、実は見た目だけでなく、全身に影響を与えるものです。歯ならびが悪いと、歯ブラシが届きにくい部分にむし歯ができやすくなったり、食べ物がしっかり噛めなかったり、発音や滑舌が悪くなったりと、さまざまなトラブルの原因になってしまいます。
いい歯ならびを育てるために、赤ちゃん時代から気をつけたいことを、歯科医の岡井有子先生にうかがいました。
歯ならびは1歳までに約8割が決まってしまう!
歯ならびにもっとも大きく影響するのは、顔や首まわりの筋肉とあごの骨格です。
筋肉と骨格がいいバランスで成長していれば、おのずと歯はきれいに並びます。反対に、このバランスがくずれてしまうと、歯列がガタガタになる、噛み合わせが深くなりすぎる、反対咬合などが起こりやすくなります。
実は、歯ならびの良し悪しは、1歳頃までには8割方が決まります。
「まだ乳歯も生えそろっていないのに?」と驚かれるかもしれませんね。
歯ならびというと、つい歯ばかりに注目しがちですが、まず目を向けたいのは普段の姿勢や動作。体にとって負担のない姿勢を保ち、バランスよく体を動かせていれば、筋肉や骨格もしっかり成長していきます。あごが発達すれば、口腔内にすべての歯がきれいに並ぶスペースができ、噛み合わせもよくなる、というわけです。

「叢生(そうせい)」と言われる歯ならび。歯が重なり合って凸凹になっています。
(写真提供:こどもと女性の歯科クリニック)
筋肉のバランスの乱れが歯ならびに影響する
赤ちゃん時代に特に気をつけたいのは、抱っこや授乳のときの姿勢です。
「抱っこひもでおでかけ中に赤ちゃんが寝てしまって、おうちに帰るまで首がガクンと後ろに倒れたままだった」なんてことはありませんか?
あごが上がったり、背中がのけぞったりする姿勢は、首の後ろや肩、背中の筋肉を過度に緊張させてしまいます。首の後ろや肩まわりの筋肉がこりかたまると、のどのあたりにある舌骨が引っぱられて、本来あるべき位置より下に落ちてしまいます。さらに舌骨が下がると、舌や下あごも下がって、気道も狭まります。
赤ちゃんが口をポカンと開けている時間が長い場合は、舌骨や下あごが下がった影響で鼻呼吸がしにくくなっているのかもしれません。
口呼吸は感染症やむし歯のリスクを高め、将来の歯ならびにも影響します。
また、近年、噛み合わせが深い過蓋咬合(かがいこうごう)のお子さんが増えていると感じます。過蓋咬合とは、奥歯で噛んだとき、下の歯がほとんど見えない噛み合わせのこと。歯列はきれいに並んでいても、前歯同士が当たって歯茎の裏が赤く腫れてしまったり、奥歯にかかる力が強すぎて、歯が欠けやすくなったりと、実はさまざまなトラブルの原因になるので注意が必要です。
過蓋咬合の原因も、舌骨が首まわりの筋肉に引っぱられ、下あごや上あごが本来の位置より下がってしまうことにあります。

過蓋咬合の例。上の前歯で下の前歯が完全に隠れてしまっています。
(写真提供:こどもと女性の歯科クリニック)
抱っこや授乳の姿勢を見直そう
抱っこや授乳のときは、赤ちゃんの背中が丸くカーブを描き、あごがおへそのほうを向くような姿勢を意識しましょう。
首や背中を反らせるクセがついてしまっている場合は、背中や首、後頭部をやさしくマッサージして、筋肉の緊張をとってあげることが大切です。
背中は、手のひら全体でやさしく上から下へとなでおろします。首から後頭部は、ゆっくりなであげて、耳の後ろへと流します。最初は嫌がっていた子も、毎日根気強く続けるうちに次第にリラックスできるようになりますよ。
お口の中のマッサージもおすすめです。歯茎をやさしくさわったり、ほおの内側をほうれい線に沿うように人差し指でなぞってあげましょう。低月齢の頃から口に指を入れられることに慣れていると、歯みがき習慣も作りやすくなります。
赤ちゃんの頃の受け口(反対咬合)などは、マッサージで筋緊張をとることで改善することも少なくありません。親子のスキンシップを兼ね、毎日の習慣にするとよいでしょう。

下の前歯が上の前歯よりも前に出ている反対咬合。受け口とも言われます。
(写真提供:こどもと女性の歯科クリニック)
たっぷり遊び、よく噛んで食べる
いい歯ならびを育てるためには、赤ちゃんの発達段階に合わせた遊びを十分にすることも大事です。ハイハイで芝生の山をのぼったり、公園を思いっきり走ったり、てくてく散歩でたっぷり歩くのもよいでしょう。ジャングルジム、すべり台など、いろいろな遊びを体験することで、体の筋肉がバランスよく発達します。足の裏から伸びる靭帯は、あごのほうまでつながっています。たくさん足を使うことは、歯ならびにもいい影響があるのです。
また、よく噛んで食べる習慣をつけることも大事です。
離乳食が始まったら、足置き板のある食事用椅子など、赤ちゃんがしっかり足を床につけられる食事環境を整えてください。食べ物をしっかり噛むためには、正しい姿勢で座ることが大切です。
離乳初期はやわらかなペースト状のものでも悪くありませんが、慣れてきたらいろいろな食感のものを取り入れていきましょう。
9カ月頃からは手づかみ食べで、自分で食べ物をつかみ、ひと口量を前歯でかじりとる練習をスタート! 手づかみ食べのポイントは、赤ちゃんの手からはみ出る大きさにすることです。指でつまめるようなひと口サイズでは、どんどん口に詰め込んでしまって、ひと口量を覚える機会になりません。噛まずに丸飲みするクセがついてしまうことも。
茹でたにんじんやふかし芋をスティック状に切ったもの、少し大きめのおにぎりなど、手のひらからはみ出る大きさを意識しましょう。
昆布、フランスパンなどをスティック状にして持たせてあげるのもいいですね。ガジガジと少しずつ噛みながら、ひと口量を覚え、そしゃくする力を育んでいきます。もちろん、のどに詰まらせたりすることのないよう、必ず大人がそばにいて見守ってあげてください。
水分補給のときには、コップを使用するのがよいです。スパウトやストローは便利ですが、歯ならびの観点からはあまりおすすめできません。赤ちゃんの骨はまだやわらかく、吸う力が加わることで、口蓋や下あごの骨がきゅっとすぼまってしまうのです。本来はアーチ状を描くはずの歯茎が、ストローを使い続けることで三角形になってしまったケースもあります。
小さなおちょこやエッグスタンドなど、赤ちゃんの口のサイズに合った容器を選ぶと、こぼさず上手に飲めるでしょう。

ストローの多用などの影響で、本来アーチを描くはずの歯列がV字になってしまっている例。
(写真提供:こどもと女性の歯科クリニック)
歯ならびが気になるときは早めに矯正治療を検討
食習慣や普段の姿勢を見直し、しっかり全身を使って遊ぶことを心がけていくと、矯正治療をしなくても次第に歯ならびが改善していくこともあります。
ただ、乳歯の段階から歯列がガタガタしている場合は、3〜4歳から矯正治療をしたほうがよいケースもあります。乳歯のほうが骨がやわらかく、動きやすいため、治療の負担が少ないことはメリット。乳歯時代から矯正をして、あごの骨格を整えると、あとから生えてくる永久歯もいい位置に並びます。
矯正治療を始める時期は、歯科医によっても違います。お子さんの歯ならびが気になったときには、信頼できる歯科医に相談しましょう。
また、むし歯や歯ならびの問題がなくても、乳幼児期から3カ月に1回程度の歯科検診を受けることをおすすめします。乳歯は、永久歯よりもエナメル質が薄く、ほんの小さなむし歯でも急激に広がってしまうこともあります。検診のときには、歯のみがき方、噛み合わせに問題がないか、歯ならびを悪くするクセがついていないか、などもチェックしてもらうといいですね。

岡井 有子/歯科医師、こどもと女性の歯科クリニック院長
産婦人科の看護師としての勤務経験、自身の子育て経験から、女性と赤ちゃん、子どもに寄り添った歯科治療を行う。顎顔面口腔育成の考え方にもとづき、あごや鼻を本来あるべき位置に成長させて口呼吸の改善をはかり、正しい歯ならびを目指す指導、治療に力を入れている。
こどもと女性の歯科クリニック:https://cw-cl.jp/