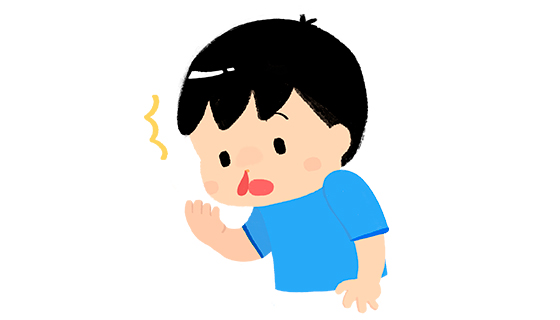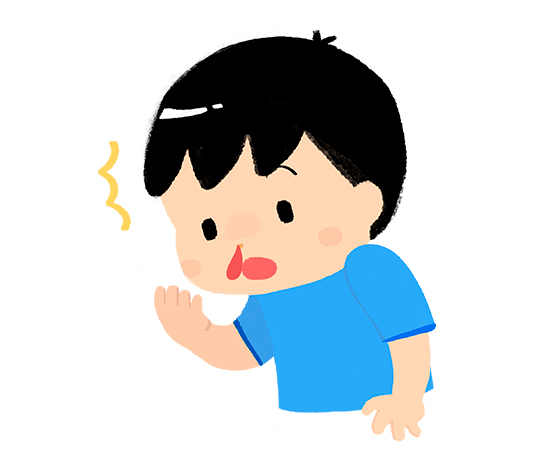mama知っ得!情報
足をくじいた!~ねんざの対処方法~

ねんざは、関節に力が加わっておこるケガの内、レントゲンに写る骨折や脱臼以外の、靭帯や腱、軟骨などのケガです。患部の関節の腫れや内出血、痛み、ぐらつき感などの症状がでます。
診断には、ケガをした時の詳しい状況確認が大切になります。関節がどのような角度で、どの方向に動いたのか、関節にどのように力が加わったのかなどを確認します。さらに、動かしたり押したりして関節に力を加えたときに痛む部分や、関節が緩くなっていないかなどを確認します。また、レントゲンで骨折がないことを確認した後、必要に応じてエコー検査やCT検査、MRI検査を行うこともあります。こうした情報を総合的に判断してねんざと診断されます。
ねんざの治療は、基本的には固定し安静を保つ保存療法です。靭帯の損傷がひどい場合には手術を検討することもあります。近年での手術は、内視鏡手術などの小さな切開で行う方法が多くなり、以前に比べて身体への負担が少なく回復が早くなってきています。固定の場合でもギプスで硬く固めた長期間の固定は行われないようになってきました。また、段階的に日常生活やスポーツなどへ復帰できるよう、回復にあわせてリハビリを行う場合もあります。
「ねんざかな?」というようなケガをした際の対処方法
ねんざなどのケガをしたときは、直後に適切な応急処置が行われることが、治りの早さ、そして日常生活やスポーツなどへの復帰の早さにもつながります。
医療機関を受診するまでの応急処置が『RICE処置』です。Rest(安静)・Icing(冷却)・Compression(圧迫)・Elevation(挙上)の頭文字をとって『RICE』と呼ばれています。
①アイスノンや氷のう(氷をビニール袋に入れたもの等)を患部に当て20〜30分ほど冷やします。
②冷えて痛みがでた後に感覚が鈍くなってきたら、氷を外して感覚が戻るのを待ちます。
③感覚が戻ったら、また氷を当てて冷やします。
これを何度か繰り返しましょう。
ねんざは、腫れや痛みなどの症状の強さは、負ったダメージの程度と一致することが多いですが、部位によっては痛みを感じにくいような場合もあります。そのため「あまり症状が酷くないから大丈夫」と安易に考えない方が安全です。場合によっては、無理をしてしまったことで患部に二次的な損傷を生じたり、それが積み重なることで変形性関節症の状態になってしまったりすることもあります。ケガをした段階で早めに整形外科へ受診をして、きちんと診断を受けておきましょう。
東京海上日動メディカルサービス 発行
http://www.tokio-mednet.co.jp/